

Fit to Standard方針で、わずか1年で基幹システムを刷新
ファイントゥデイインダストリーズの挑戦
導入製品
資生堂からの独立に伴い、移行サービス契約(TSA)により基幹システムを1年以内に構築する必要があったファイントゥデイインダストリーズ。通常2年かかる規模のシステム導入を短期間で実現するため、日本のきめ細やかなものづくりにフィットするmcframe 7を選定。
期日・コストの制約が極めて大きいため、パッケージ標準に業務を合わせるFit to Standardで導入を進めた。経営層の揺るがぬ方針のもと、Fit to Standardの勘所を押さえたプロジェクト推進、それぞれが役割を理解した主体的な活動、さらに導入パートナーであるキッセイコムテックの垣根を越えた協働により、カスタマイズを最小限に抑えながら計画通りの稼働を実現した。
2021年7月、資生堂からパーソナルケア事業を譲り受けて誕生したファイントゥデイ。同社はヘアケアブランドの「TSUBAKI」や「fino」、スキンケアブランドの「SENKA」「uno」ボディケアブランドの「SEA BREEZE」など、日本の生活者に愛され続けてきた数々のブランドを引き継ぎ、独立した企業として新たなスタートを切った。
「世界中の誰もが、素晴らしい一日を紡ぎ、いつまでも美しく、豊かな人生を送れるようにする」というパーパスを掲げ、ブランドマーケティングから技術開発、生産、販売に至るまで、自社で一貫して提供する体制を構築している。「ヘアケア」「スキンケア」「ボディケア」の3分野を軸に、世界中の人々の生活を彩る多様なブランドを展開している企業だ。
ファイントゥデイという社名には「Making every day a fine day」という創業時の思いが込められている。それは「今日という限りある一日を、心豊かに過ごしていただきたい」という願いであり、日々の生活を少しずつ良くしていこうという決意の表れでもある。
同社は資生堂が100年以上大切にしてきたブランド価値や美意識を引き継いでおり、この美意識を礎として、「単なる日用品」を超えて、「毎日を豊かにする素晴らしい製品」を提供することを目指している。
資生堂の久喜工場を前身とするファイントゥデイインダストリーズ株式会社は、ファイントゥデイの生産事業を担っている。資生堂からの独立には大きな課題があった。資生堂との移行サービス契約(TSA)により、基幹システムを含むすべてのインフラを期限内に切り替える必要があったのだ。通常なら2年はかかる規模のシステム導入を、わずか1年で完遂しなければならない。

短期間でのシステム導入を実現するために、会計・販売などのバックオフィスの業務領域にはSaaS型のERP、生産・原価などのものづくりの業務領域にはmcframeを選定する方針とした。
mcframeを選定した理由は明確だった。ファイントゥデイのPM(プロジェクトマネージャ)の後藤章一氏は以下のように語る。「大きくふたつの理由がありました。ひとつは日本の製造業への導入実績が豊富なこと、もうひとつは、パッケージの仕様を深く理解し、導入経験が豊富なパートナーが存在することです。」
会計・販売などのバックオフィスの業務領域と異なり、ものづくりの業務領域においては、日本のきめ細やかなものづくりにフィットする製品を採用した方が安心であると考えた。また、導入パートナーのキッセイコムテック株式会社(以下、キッセイコムテック)が、提案時にmcframeにできること・できないことや代案を明確に回答できたため、あとはファイントゥデイが業務を変更するのか、システム外で対応するのかなどを判断すればよく、限られた期間でシステム導入していくうえで、信頼できるパートナーと感じたと後藤氏は語る。

一方、導入パートナーとなるキッセイコムテックとしては、1年でのシステム稼働が必達ということに不安もあった。PMの伊藤淳矢氏は「もしお話を聞いて、ひと言でも『カスタマイズ』という言葉が出たら、提案を辞退することを考えていた。」と当時を振り返る。しかし、ファイントゥデイのCIOの小澤稔弘氏からは「カスタマイズ」という言葉は発せられず、代わりに「期日・コストの制約が極めて大きいため、パッケージ標準に業務を合わせる『Fit to Standard』の方針を徹底する」との考えを強く持たれていることがわかり、提案を進めていくことを決断した。
こうしてFit to Standard方針でのプロジェクトが2023年初頭にスタートした。
経営層はシステム構築の原則として、「Fit to Standard」の方針に加えて、「D>C>Q」という明確な優先順位を打ち出した。QCDとは一般的にQuality(品質)、Cost(コスト)、Delivery(納期)の頭文字を取った略語である。今回のプロジェクトでは、“Q”を機能網羅性として捉え、TSA期間中(D)に限られた予算(C)で早期に構築する必要があるため「D>C>Q」の優先順位とし、効率化や高度化のための個別対応については、必要があれば2次開発で対応する方針とした。また、期間(D)・費用(C)を抑えるために、自分達でできることは自分達で対応することを指針とした。

また、D>C>Qの方針を徹底するために、ファイントゥデイでは「Fit to Standard審議会」を設置し、ROI(投資対効果)の観点からトップダウンでアドオン要否を判断する枠組みとした。「Fit to Standard」と「D>C>Q」という明確なプロジェクト方針、そしてFit to Standard 審議会の枠組みが功を奏し、迅速に検討や意思決定が進み、結果的にアドオン機能も業界特有の法対応や顧客対応の帳票と他システム連携などの要件に限定することができた。
「経営層がもし『もう少しお金をかけてもいいから可能な範囲でQも』と発信したり、途中でプロジェクト方針がブレるようなことがあれば、3年かかっても稼働していなかったでしょう。」と後藤氏は振り返る。経営層の明確かつブレないプロジェクト方針がプロジェクト全体のベクトルを生み出し、短納期での安定稼働の大きな原動力となった。
ファイントゥデイの独立運営に不可欠なこの重要プロジェクトのPMを任せられたのが、システム刷新を機にファイントゥデイに入社した後藤氏だ。
後藤氏は複数社を渡り歩くキャリアのなかで、ユーザー側のPMとベンダー側のPMの双方の経験を持ち、両者の観点でプロジェクトを俯瞰し、過去の複数のプロジェクトを通して得た知見からリスクポイントを想定できるまさに“プロPM”だ。
後藤氏は、「明確なプロジェクト方針、現行の業務・システムを熟知しているユーザー部門とIT部門、導入実績豊富なパッケージ、パッケージの仕様を深く理解し導入経験豊富なパートナーという盤石なスキームのため、必ずうまくいくだろう。」と捉えていたという。
また後藤氏は、生産計画、生産実行、購買、原価管理などの領域ごとのリーダーをBIZ(ユーザー部門)・IT(情報システム部)・ベンダー(キッセイコムテック)の3リーダー体制とし、それぞれの役割やフォーカスすべき範囲を明確にすることで、協力して推進できる体制とした。後藤氏は、「ITシステムを入れることが目的ではありますが、ビジネスプロセスとシステムはセットで、ビジネスプロセスを充足するためのシステムという側面もあります。また、インターフェイスやセキュリティなどITとしての専門領域もありますし、パッケージ仕様のことはベンダーに聞かないとわかりません。そのため、それぞれのフォーカスポイントを明確にし、協力し合える環境づくりを心がけました。」と、そのねらいを語る。


ベンダー側のリーダーを務めたキッセイコムテックの黒岩俊太郎氏と亀野剛氏は、「ユーザー部門、IT部門、ベンダーそれぞれの役割が明確だったので、ショートミーティングで適宜コミュニケーションをとりながら、迅速に課題解決を進めることができました。」とその効果について語る。
後藤氏は、今回のプロジェクトではスキームレベルの問題はないため、基本的な部分では大きな問題は発生しないだろうと想定していた。一方、部門間の業務連携やシステム間の連携については一般的にトラブルが多く、移行・テスト工程にその皺寄せが出やすいため、迅速に解決できるよう体制や段取りを丁寧に組むアプローチとした。
具体的には、マスタ準備のタスクにおいては、主体的に動き、周囲への働きかけができる人、自走できる人の存在が不可欠なため、設計部門からそのようなパーソナリティを持つ人をアサインしてもらった。
システムテスト/受入テスト/運用テストでは、伝統的な手法ではあるが、業務部門・IT部門・ベンダーがオンサイトでひとつの部屋に集まり、業務部門毎に島をつくることで、迅速に部門間やシステム間の課題を解決できるようにした。
移行では、移行手順書や本番移行時のタイムチャートを作成し、テストと同様の体制で移行リハーサルを3回実施することで入念に準備した。
本稼働後のハイパーケア期間も同様にオンサイトで即応できる体制をとったが、前工程で問題をつぶし込めていたため、計画していた2カ月から1ヶ月に期間を短縮でき、大きなインシデントもなく安定稼働できたことは大きな成果といえるだろう。
パンデミック以降、オンラインを主体とするプロジェクトも増えているが、後藤氏はオンラインを活用しつつもオンサイトが有効な場面も熟知しており、場面によって使い分けることで、効果的なプロジェクト運営を可能とした。


経営層から明確なFit to Standardの方針が出される一方で、長年業務・システムを支えてきた業務部門・IT部門には不安や戸惑いもあった。
IT部門の吉村健一氏は、「これまで業務要件を定義したうえでシステム要件を定義する方法しかやってこなかったので、パッケージ標準に業務を合わせるFit to Standardの考え方は、カルチャーが違い過ぎてイメージが湧かず、本当にこれでうまくいくのだろうかと不安を感じていました。」と当時を振り返る。
生産管理部門を統括する橋本健二氏も、「パッケージの説明を受けても、mcframeとファイントゥデイとでは用語が異なるため、意思疎通がうまく取れない場面もありました。」と振り返る。一例として、ファイントゥデイではシャンプーなどの中身液をつくることを「製造」、充填・梱包することを「生産」と呼称するが、mcframeではどちらも「製造」と呼称するなどの違いがあり、当初はうまく話が噛み合わない場面もあったという。

これらの不安や戸惑いはFit to Standardアプローチでは不可避なものともいえるが、どのように乗り越えていったのだろうか。
橋本氏は、「キッセイコムテックさんが我々の業務を理解し、ファイントゥデイとmcframeの用語の違いを丁寧に翻訳しながら説明してくれたおかげで、言葉が通じ合うようになり、社内のコミュニケーションもよくなっていきました。」とキッセイコムテックの対応を評価する。キッセイコムテックの伊藤氏は「顧客の業務を理解し、顧客の言葉で伝えることは、ベンダーの責務です。」とその理念を語る。
ユーザー部門からIT部門に異動し、プロジェクトで専任担当となった守谷日向子氏も、「私も現場の人もシステムに詳しいわけではなかったので、プロジェクト初期はよくわからない点があったり、キッセイコムテックさんから 提案の良し悪しを聞かれても、答えられないこともありました。ただ、わからないまま進むのはストレスですし、モヤモヤをためるのもよくないので、『何がわからない? 何に困っている?』など社内でざっくばらんに会話するようにしていきました。キッセイコムテックさんは何回も同じようなことを聞いても快く答えてくれて、和やかな雰囲気で、前向きであたたかな対応をしてくれてありがたかったです。」とキッセイコムテックの姿勢を評価する。

また吉村氏は、「セッションを進めるうちに、mcframeの業務コンセプトと自社の業務コンセプトに大きなズレがないことがわかり不安が解消していきました。自社の業務の考え方がスタンダードに近いことがわかり、自分達がやってきたことは間違いではなかったと自信を持つこともできました。」と語る。日本の製造業で鍛えられたmcframeが、日本の製造業にフィットするスタンダードを持っていることも大きかったようだ。
ファイントゥデイのモヤモヤをそのままにしない雰囲気づくりとキッセイコムテックの顧客に誠実に向き合う姿勢、日本の製造業に鍛えられたmcframeのスタンダードが、Fit to Standardへの不安や戸惑いを消し去っていった。
前述の通り、本プロジェクトでは「D>C>Q」の優先順位を掲げていたが、D(期間)・C(費用)の達成を強固なものにするために、「自分達にできることは自分達で」を基本的な指針としていた。
例えば、適用検証フェーズをスムーズに進めていくために、IT部門が自主的に事前に業務部門にヒアリングし、業務フローを整理していたという。この効果を専任担当として対応した守谷氏は次のように語る。「プロジェクト前は自分が担当したことのある業務しか知見がありませんでしたが、事前にヒアリングしていたことで、業務全体を理解するきっかけになり、その後のフェーズで大いに役立ちました。」
その後もプロトタイプの実施においては、業務プロセスのパターンの洗い出しからプロトタイプ環境、業務シナリオ、データの準備など、自分達でできることは自分達で進めていった。
マスタ移行においても、設計担当がリーダーとなり、部門横断でチームを組成し、各担当がそれぞれmcframeを理解し、自分事化できたことも大きいという。例えば、品目マスタひとつとっても、技術部門、生産部門、物流部門、検査部門など、関係する部門は多岐にわたる。業務を体系的に整理し、誰が、いつ、どのように使う項目なのか、マスタと業務の関連性を明確にし、上流から下流まで業務の流れを部門横断で意思疎通しながら進めていくことで、精度よくマスタを移行することができたという。
一方で、mcframeの仕様のことなどは自分達にはわからないので、キッセイコムテックに遠慮なく聞くようにし、キッセイコムテックも迅速に解決策やアドバイスを提示した。
このように「自分達にできることは自分達で」という主体性が関係者間の調和を生み出し、歯車が噛み合うことで、想定を上回る形でのD(納期)・C(費用)の達成 につながった。
今回はビジネス環境の制約によりシステムを刷新することになったが、現行の業務・システムに何か問題は抱えていたのだろうか。吉村氏は次のように語る。「既存システムについては 、正直なところ大きな問題を感じているわけではありませんでした。ただプロジェクトを進めていくにつれて、業務が固定化していたり、データ取得で属人的な部分があったり、データが社内のシステムや文書に散在しているなど、問題があることもわかってきました。」
既存システムはパッケージではなくスクラッチ開発 していたこともあり、各部の要求に微に入り細に入りきめ細かく対応され、それはそれで使いやすいものだったが、長年作り込まれていくうちに、いつしか業務がシステムにより固定化したり、個別最適化したりする部分もあったのだ。
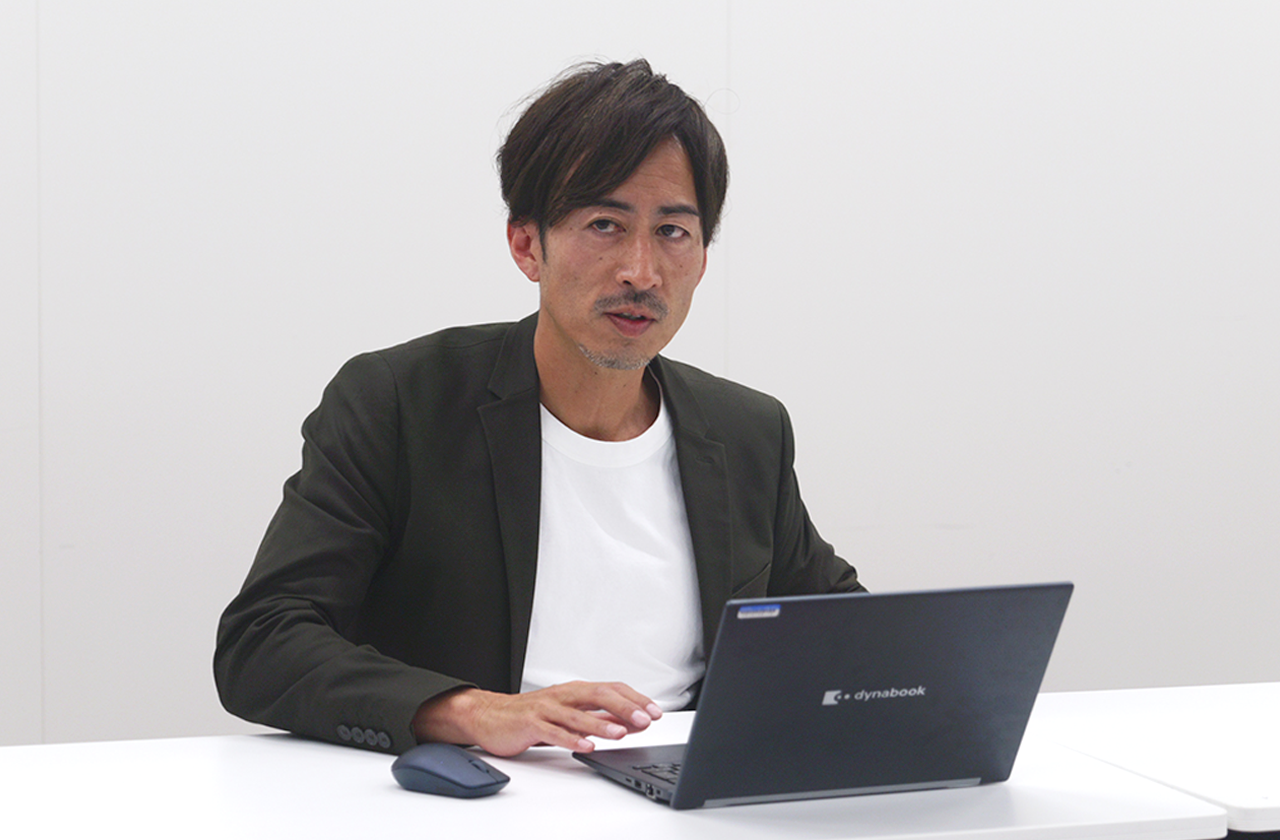
IT部門の小森章弘氏は次のように語る。「データ取得においては、個別対応を繰り返してきたなかでSQLのスクリプトが300本ほど存在していました。これらを棚卸し、要否を判断したうえで仕様をドキュメント化し、新旧比較もしたうえでmcframeのデータ出力ツールに内製で実装しました。」
また、マスタ移行においても、単に既存システムから移行するだけでなく、システムや文書に散在していた情報を集約し、mcframeの汎用マスタという仕組みを利用して、業務に必要な製品に関する情報を一元管理できるようにしたという。
『Fit to Standard』というと自社の強みも弱みも特徴も消し去って、スタンダードをそのまま鵜呑みにしていくような響きもあるが、ファイントゥデイでは企業内にある資産を丁寧に棚卸し、負の遺産とは決別し、資産はきちんと資産化して継承する地道なアプローチをとったのだ。
いつしかパッケージ標準に業務を合わせる『Fit to Standard』の方針でありながらも、自社の業務やデータとmcframeの仕様を深く理解し、mcframeをツールとしてうまく活用することで、逆説的ではあるが、自社のあるべき姿にシステムを合わせていくような状態になっていった。

一方、システムインフラについては、D>C>Qを実現し、限られたITリソースで安定的に運用していくために、ファイントゥデイはSaaSやPaaSを組み合わせてシステム構築することを基本方針としていた。
この方針に対応するために、キッセイコムテックはmcframeを従来のオンプレミス型ではなく、クラウドサービスのように利用できる疑似SaaSとして提供した。セキュリティ面においても、ゼロトラストセキュリティへの対応として、WAF (Web Application Firewall) の導入、SAML認証システムの構築、定期的な脆弱性診断、ペネトレーションテスト等を実施し、これらの包括的なセキュリティ対策により、安全で信頼性の高いシステム環境を提供している。
プロジェクトで刷新されたのは業務・システムだけではない。関わったひとりひとりの成長やプロジェクトを通して築かれた人と人の絆もそのひとつだ。
守谷氏は次のように語る。「ユーザー、管理チーム、ベンダーそれぞれの立場を中立的・俯瞰的に見られるようになりました。プロジェクト前は一ユーザーとしての立場のみで、視野が狭いところもありました。今は、上司や周囲の人がどのようなことを考えてこの発言をしているのか、表面的な内容だけでなく、その背景に考えが及ぶようになり、今まで以上に深く相手や内容を理解できるようになりました。」
キッセイコムテックの伊藤氏も「守谷氏の上司である吉村氏は、こういったことは自分達でやるべき、こういったことは遠慮なくキッセイコムテックに質問すべきなどの軸を明確に持たれていて、そうした一貫性や風土づくりが、プロジェクトの成功だけでなく、各人の成長に寄与する部分も大きかったように感じている。」と振り返る。
吉村氏自身も「5年後、10年後を自分達でつくっていくという意識が今まで以上に強くなりました。」とプロジェクトを通しての変化を語る。
システム刷新の計画通りの成功はもちろんだが、プロジェクトを通してひとりひとりの視点、視野、視座が向上し、個人としても組織としても成長したことは、ファイントゥデイにとって大きな果実といえるだろう。
システム導入の成果について後藤氏は次のように振り返る。「D>C>Qという指針を掲げていましたが、D(期間)についてはスケジュール通りに稼働し、稼働後のハイパーケア期間も半月短縮して安定稼働という成果を得ることができました。C(費用)についても1次開発を最低限必要なものに抑えられたうえに、2次開発についても業務・システム・データが噛み合って稼働したことで、当初見込んでいたほど要求が上がりませんでした。結果的に投資対効果の高いシステムを導入できたといえます。」
業務面でも大きな効果が現れている。mcframe導入によりデータが整理され、一元管理が実現された点だ。橋本氏は「ひとつの箱からさまざまなデータを取得できるようになったので、使い勝手が非常に良くなりました。」とその効果を語る。後藤氏も「導入から1年経過し、データが蓄積されてきました。今後はデータを分析し、活用していくことに取り組んでいきたい。」とその展望を語る。
限られた時間の中で、パッケージ標準導入による業務整理や意識の変化など、大きな変革を成し遂げたファイントゥデイ。その成功の背景には、トップの揺るがぬ方針、現場の不安に寄り添う丁寧なコミュニケーション、それぞれが役割を果たす主体的な推進、そしてユーザーとベンダーの垣根を越えた協働があった。
「ひとりひとりが成長し、よりよくしていこうという考え方。それは外見や製品だけでなく、自分の仕事や日々の行動にも美意識を持つということです。」と後藤氏は語る。
mcframeという基盤を得て、同社は「Making every day a fine day」という理念のもと、世界中の人々に美と豊かさを届ける使命に向けて、新たな成長への道を力強く歩み始めている。

執筆:大西 茉那(B-EN-G)
| 商号 | 株式会社ファイントゥデイインダストリーズ |
|---|---|
| 設立 | 2022年9月1日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 従業員数 | 624名(2024年12月) |
| 事業内容 | パーソナルケア製品の生産等 |
※本事例及び発言者の部署、肩書は2025年5月取材時点の内容です。
※本事例中に記載の肩書きや数値、固有名詞等は掲載当時のものであり、変更されている可能性があります。
※掲載企業様への直接のご連絡はご容赦ください。
Copyright(C) Business Engineering Corporation. All rights reserved.