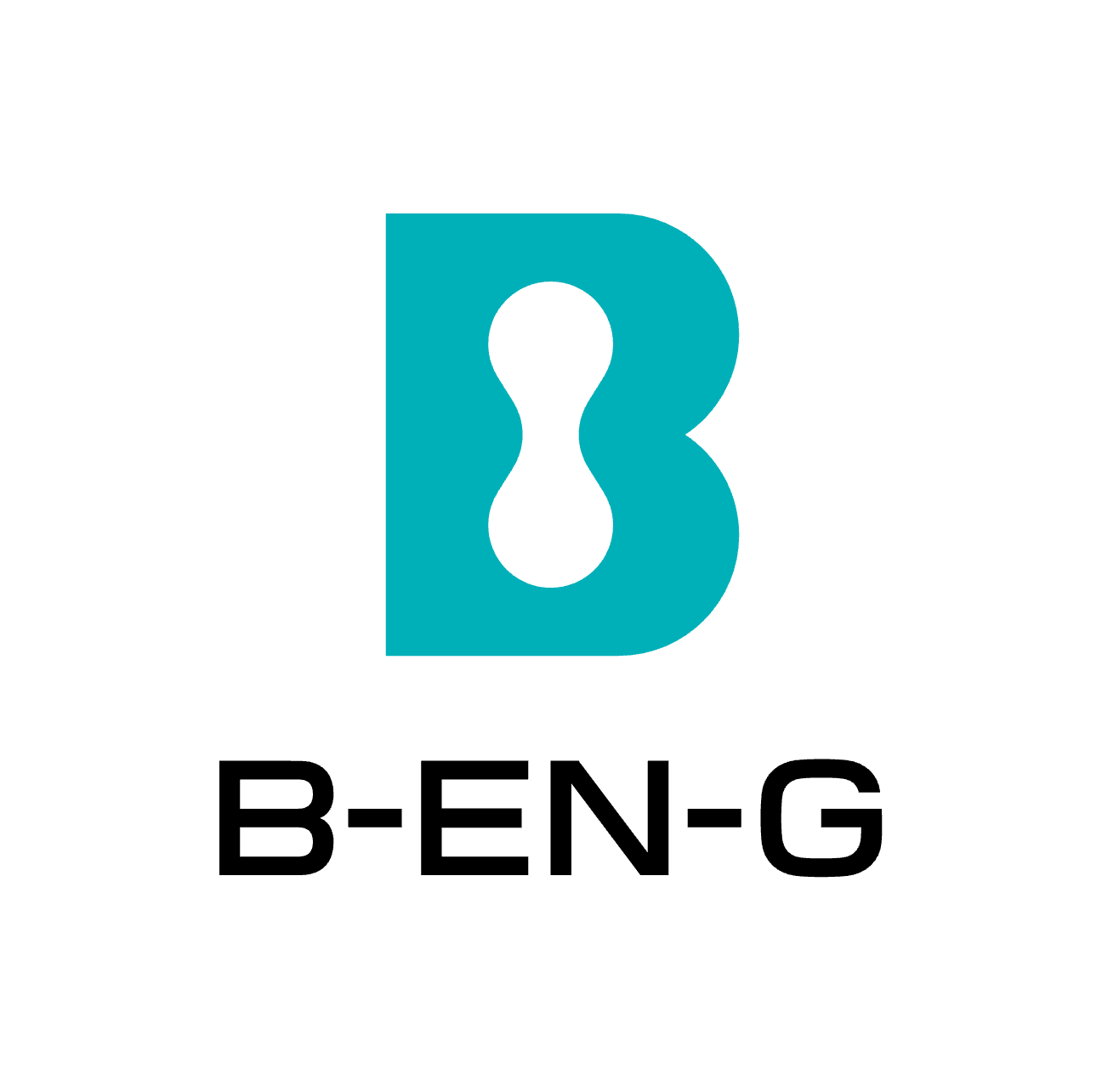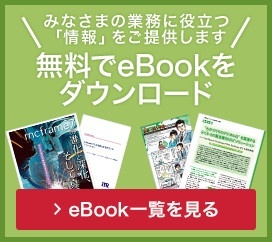mcframe Day 2019セッションレポート DXとERPの連携で10年先を見据えた競争力のある経営システムの実現を目指す

2019年11月28日、JPタワーホール&カンファレンス(東京都千代田区)において、ビジネスエンジニアリング(B-EN-G)が主催する年次イベント「mcframe Day 2019」が盛大に開催された。本稿では、オープニングキーノート「これからの基幹業務システムの話をしよう」で語られた要点を紹介する。

大勢の来場者が詰めかけた会場で、まずステージに登場し、挨拶したのは、代表取締役・取締役社長の大澤正典だ。「mcframe Day 2019のキーワードは、“基幹業務システム”です。デジタルの時代に、なぜ基幹業務システムの話なのかと思われるかもしれませんが、日本の製造業が、今後の基幹業務システムのデザインやデジタル化をいかに推進していくか。その興味は尽きません。このテーマが今後の皆様のお役に立ち、ひいては日本の製造業の活性化に役立つと確信しています」と大澤は語る。
続くオープニングキーノートは、「これからの基幹業務システムの話をしよう」をテーマに、パネルディスカッション形式で実施された。パネラーは、ヤマハ発動機 フェローの平野浩介氏、およびB-EN-G 専務取締役の羽田雅一の2名。モデレータは、アイティメディア メディア事業本部 テクノロジー局 MONOist編集部 編集長の三島一孝氏が務めた。
ITはコストではなく投資である

まず平野氏は、ヤマハ発動機がデジタルトランスフォーメーション(DX)に舵を切った理由を明かした。二輪車を大きな柱としてグローバルで事業を展開するヤマハ発動機は、近年では次世代パーソナルモビリティの開発をはじめ先進的な取り組みにも注力している。しかし平野氏は、「弊社は、品質、コスト、納期に重点をおいた典型的なモノづくり企業であり、お客様起点を謳っていますが、顧客情報がほとんどなく、十分にリーチできていない状況でした」と課題を示した。平野氏が同社にジョインしたのは2017年4月。そこで期待されたのがヤマハ発動機のDXを推進することであった。
「DXの推進には、最初に経営層と十分な時間を使ってビジネスのあり方をディスカッションし、目的意識をあわせました。2025年、2030年に、ヤマハ発動機がどんな会社でありたいか、そのためにはどうすべきか。こうした目的を全社で共有することからスタートしています」と語る平野氏。次には、経営課題や経営戦略に対し、デジタルが成し得るインパクトを共有し、「ITはコストではなく投資であり、IT投資によってスタートアップにはない技術資産という強みを生かすことができることを説明しました」と平野氏は話す。
なおヤマハ発動機では、DXにより目指す具体的な姿として次の3つを掲げている。
- (1)予知型経営、課題解決型/戦略的思考型により、10年先を見据えた競争力のある経営システムを実現する
- (2)既存事業をデジタルで強化する
- (3)5000万人の顧客と新たなビジネスを共創する
これらを成し遂げるにあたっては、「まずは分散したデータを統合し、迅速な意思決定を可能にする仕組みの構築が必要でした」と平野氏は説明する。
DXになぜERPが必要なのか

続いてモデレータの三島氏は「DXになぜERPが必要なのか」というテーマでディスカッションを進めていった。平野氏は「DXが目指すのは、あくまでもビジネスの成長です。ビジネスを成長させるためには、オートバイやボートなどの乗り物や、スマートファクトリーから収集されるデータを解析し、お客様とつながることで、ビジネスを協創することが必要になります」と語った。
ヤマハ発動機では、海外110社、国内24社が独自のシステムを運用していることが少なくなく、本社だけでも130以上の内製ソフトが稼働している。この部分最適のシステムを全体最適にするためには、まずは130以上の内製ソフトのデータベースを1つに統合し、土台となるIT基盤を整備することが必要だ。
「最終的には、ERPによりグローバルで統合し、ビジネスにどれだけ貢献しているかをリアルタイムに見える化することで、予知型経営、課題解決型/戦略的思考型による、10年先を見据えた競争力のある経営システムの実現を目指しています」と平野氏は語った。
一方、ERPを提供する側としての考えはどうであろうか。三島氏は、「DXにおけるERPの関連性をどのようにお考えになっているでしょうか」と質問を投げかけると、羽田はこう答えた。
「DXとERPのつながりでいうと、IoTの存在は大きいでしょう。例えばパトライトのAirGRIDとB-EN-Gのmcframe SIGNAL CHAINにより生産技術と設備をつなぐことで、これまでは難しかった効率的な稼働モニタリングや設備メンテナンスを実現できます。また、モーションセンサーで作業者の動作や姿勢を3次元データ化するmcframe MOTIONでは、生産技術と人をつなぎ、作業指導、作業保証、作業負荷の分析・評価システムを実現できます」。
もっとも、これで終わってはIoTの部分最適でしかなく、ビジネスにインパクトを与えているとまではいえない。目指すのはさらにその先の世界だ。例えばIoTと生産管理がつながることでトレーサビリティが深化し、より高い安全性の確保が可能になる。また、IoTと原価管理がつながることで、原価計算のスピードと精度の向上が可能になり、利益の追求といった大きなビジネスインパクトが期待できる。
「特に、原価管理はIoTと連携することで革命的な変革をもたらすことができるでしょう」と羽田は語る。例えば次のような状況を想定してみるとよいだろう。ある会社Aは古い部分最適のERPのままであり、一方の会社BはDXとERPを全体最適でしっかりとつないでいる場合、もし両社が同等の製品力と現場力を持っていても、その競争力には大きな差が生まれてくる。精度の高い原価管理ができていれば、競合が製品の値段を下げた場合、原価の最も安い拠点に生産を移すといったダイナミックな対応も可能になるからだ。
グローバルで勝負するためにはERPが不可欠

このように、部分最適から全体最適に変革するためにはDXとERPの連携が不可欠になってくる。ERPは1990年代後半から導入され、企業における歴史は長いが、なぜいま見直さなければならないのか。従来のERPとDXと連携するERPは何が違うのだろうか。
次に羽田はある数字を紹介した。ある調査によればERPを導入している日本の製造業は3~4割に過ぎないといい、残りは独自システムを使い続けているという現状だ。後者の企業では、担当者が辞めるとだれも触れない属人的な仕組みとなっているケースが多い。3~4割しかサプライチェーンがシステム化できていないということは、システム化するだけでも国内では差別化につながるということになる。
「これまでの日本の製造業の強みは、徹底的に品質にこだわってきたことにあります。日本は、単一民族で、単一言語、単一文化である日本独自の『人間系の強み』を活かして成長することができました。そのため、独自のシステムでも競争力を維持できたのです。しかし、この状況はビジネスのグローバル化で一変しました」と羽田は説明する。
海外の企業は民族も言語も文化も違う中で、業務を円滑に遂行するために「仕組み・仕掛け」が不可欠になる。だからこそERPによる標準化が不可欠なのだ。「ビジネスのグローバル化により、日本の製造業も人間系の強みだけでは対応できなくなり、ERPを導入しなければ競争力を維持できなくなってきたのが実情です」と羽田は強調する。
また平野氏も「グローバルで勝負するためにはERPが不可欠です」として、羽田の考えに賛同した。
「ITは投資といいましたが、DXのためには初期投資も必要です。この費用をどのように捻出するかが重要になります。同時に、ERPの導入も必要なため、3~4年は二重投資になります。ただし、5年後、10年後を見据えたときに、SoR領域に関してはERPの標準機能を活用して投資を最小限にしながら、SoEの領域においては最大の投資をすることが必要です」(平野氏)。
ヤマハ発動機では、現在約1800人の豊富なIT人材を有している。平野氏は「例えばSAPはグローバルで10万人近い従業員のうち7万人がERPの開発にかかわっているといいます。もちろんそれに比べると弊社の人員は微々たるものに過ぎず、システム開発力で勝てるはずがありません。そこでSoR領域はERPで標準化し、デジタル化に1800人のIT人材を投資していきたいと思っています」と意気込みを示した。
「2025年の崖」を克服するためには何が必要か
2018年に経済産業省が公開して大きな話題になったのが、『DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~(*1)』だ。次に三島氏は「『2025年の崖』を克服するためには何が必要でしょうか」とというテーマでディスカッションを進めていった。
まず、経済産業省のDXレポートの中には、「2025年の崖」を克服するためには、基幹システムを市場の変化に追随させなければならないと言及されている。これを踏まえて羽田は「既存の基幹システムは、属人的な仕組みで過剰なカスタマイズのため、保守に多大な工数がかかっています。DXの進化に対応するためには、システムマネジメントが容易で、ビジネスモデルの変化に追随できる仕組みが必要です。作りこみの機能を最小化し、できる限りERPの標準機能を活用することが重要になります」と訴えた。
なおB-EN-Gでは、mcframeをリリースして20年以上経つため、ユーザー会などを通じて、お客様からの数多くのフィードバックを得ている。「100点とまではいわないものの、かなり使える仕組みはできたと思っています。同時に、機能をシンプル化し、管理を容易にして、変化に対応しやすい仕組みを実現しています」と羽田は語る。
だが、企業規模が多くなれば、できるだけERPの標準機能を活用する合意も難しくなるのではないか――。こう疑問を投げかける三島氏に対して平野氏は、「確かに大変ですが、ヤマハ発動機では、当初より『本当にやるんだ』という意気込みがあり、経営層も含めて、原理原則を確立することで合意し、そこから具体案に落とし込んでいきました」と答えた。
その具体案としてヤマハ発動機では、IT部門だけでなく、業務部門主導でERPをベースに業務プロセス改善のための組織も作っている。業務プロセスが決まったら、IT部門がERP上に実装するためのテンプレートを作成する。このテンプレートをグローバルにも横展開することを目指しているのだ。
「ERPをベースに業務プロセスを改善することに対し、現場の抵抗もありましたが、ERPが進化していることを説明し、納得してもらいました。例えば、以前のMRPは使いこなすために、かなりのスキルが必要でした。現在は人工知能(AI)を活用することで、かなり簡単かつ正確にMRPを回せるようになっています。AIよりいいものができるのであれば考えてほしいと現場に納得してもらいました」(平野氏)。
製造業が培ってきた技術をデジタルやデータ武装する
企業の競争の戦場がグローバルへと移る中で、今後、日本の製造業はさらなる進化を続けなくてはならない。「ヤマハ発動機は、世界に誇れる強い技術を持っています。この技術はシリコンバレーのスタートアップも持っていない技術で、これを生かすべきだと思っています」と平野氏は強調する。
もちろん、いままでのやり方やいままでの技術のままで、5年後、10年後に勝てるほど単純ではない。その部分において、「デジタルやデータで武装して、これまでの強みとかけ合わせることで、明るい未来がやって来ると確信しています」と平野氏は語った。
最後に羽田も、「DXの取り組みは、日本の製造業に向いていると思っています。DXは、実際に体験しなければ分からないことも多いのですが、実際に体験してみて、現場から経営層にフィードバックすることは日本の製造業は得意です。こうした取り組みで、DXを推進することにより、日本の製造業に明るい未来が開けると思っています」と話した。
(*1)DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/20180907_report.html