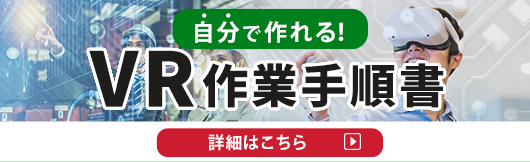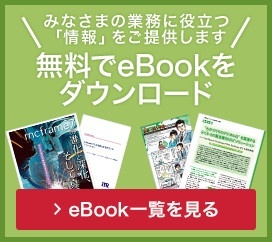OJTのよくある失敗例

OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)は、新人の育成において非常に有効な手法ですが、適切に運用されないと逆効果になることもあります。現場で実務を通じてスキルを学ぶことは、座学では得られない実践的な知識を習得できる大きなメリットがあります。しかし、OJTの成功には、適切な計画、効果的な指導、継続的なフィードバックが不可欠です。
しかしながら、現場の忙しさや指導者の意識不足などが原因で、OJTが形骸化してしまうケースも多く見られます。「見て覚えろ」「やりながら学べ」といった曖昧な指導方法が主流になってしまうと、新人は何をどう学べばよいのか分からず、成長の機会を失ってしまいます。その結果、新人のスキル習得が遅れるだけでなく、職場全体の生産性やチームの連携にも悪影響を及ぼすことになります。
第四回の今回は、OJTのよくある失敗例を紹介し、その背景や問題点を掘り下げていきます。失敗の要因を理解することで、より効果的なOJTの実践に向けた改善のヒントを探っていきましょう。
OJTはその性格上、現場で現物を確認しながら実施することが多くなります。よって、現場任せの指導になる可能性が高く、また指導する側も自分のこれまでの経験をもとに指導するため、価値観の違いや指導方法の違いなどのギャップ(前回コラム参照)により、結果としてその効果が十分に発揮できないことが起こりがちです。では、具体的な失敗事例をもとに、その原因や対策について考えてみましょう。

1. 計画性のないOJT
ある製造現場では、新人に対して「とりあえずやってみろ」という形で業務を任せることが常態化していました。しかし、明確な手順や目標が示されていないため、新人は何をどのように習得すべきかが分からず、曖昧なまま仕事を進めることになりました。その結果、ミスが多発し、指導者側も「何度言っても覚えない」と不満を募らせるという悪循環に陥ってしまいました。
その背景には、計画性のないOJTがありました。指導者側が十分な準備をせずに場当たり的な指導でOJTを実施することで、指導する側、される側でのギャップが大きくなり、上記悪循環が生まれているようでした。特に、中小企業などでは、体系的なOJTの枠組みがないまま指導者の裁量に任せるケースが多く、新人が何をいつ学ぶべきかの指針が明確になっていません。また、指導者自身が業務に忙殺されることで、新人の育成が後回しになりがちです。
改善のポイント: OJTを効果的に進めるためには、事前に研修計画を策定し、新人がどのタイミングでどの業務を習得するのかを明確にする必要があります。具体的な目標を設定し、段階的な成長を促すことで、新人が混乱することなくスキルを身につけられるようになります。また、指導計画を作成する際には、業務の流れを考慮し、「何を・どの順番で・どの程度の期間で」習得させるかを具体化することが重要です。さらに、指導者同士で情報共有を行い、新人が一貫性のある教育を受けられる体制を整えることも効果的です。
2. 指導者による丸投げ
指導者が忙しさを理由に新人教育を十分に行わないケースも多く見られます。「見て覚えろ」というスタンスで放置された新人は、適切な知識を得ることができず、結果として成長が遅れてしまいます。ある現場では、指導者が「自分の仕事で手一杯だから、新人は先輩のやり方を見て学ぶべきだ」と考えていました。そのため、新人が業務の流れを十分に理解しないまま作業を進めることになり、ミスが頻発。新人は「聞いても教えてもらえない」「どうすればいいか分からない」と不安を抱え、早期退職につながってしまいました。
これらの背景には、指導者の意識の問題だけでなく、職場全体の教育体制の不備が関係しています。指導者にOJTの重要性が十分に伝わっていない場合や、指導者自身が新人教育に関する研修を受けていない場合、このような事態が発生しやすくなります。
改善のポイント: 指導者には、新人教育の基本的なスキルを学ぶ機会を提供することが重要です。また、指導者自身の負担を軽減するために、複数の先輩社員が連携して新人を指導する体制を整えると効果的です。具体的には、OJTを担当する指導者に対して「指導技術研修」を実施し、効果的な教え方やコミュニケーションスキルを習得させることが望ましいでしょう。また、指導者が一人に偏らないように、ローテーション制を導入し、複数の指導者が関わることで新人の視点を広げることも効果的です。
3. 適切なフィードバックの欠如
また、ある企業では、新人に対して指導は行われるものの、進捗確認やフィードバックがほとんどありませんでした。結果として、新人は「このやり方で合っているのか?」「どこを改善すればよいのか?」と不安を抱えながら業務を進めることになり、学習効果が著しく低下しました。結局、新人の定着率が悪くなり、組織全体の生産性にも影響を及ぼす結果となりました。OJTにおいて、適切なフィードバックがなければ、新人は自分の成長を実感できず、モチベーションを維持するのが難しくなります。
改善のポイント: 新人に対して、定期的なフィードバックを行うことが重要です。具体的な改善点を伝えるだけでなく、できている部分を明確に評価することで、新人の自信を育むことができます。フィードバックを行う際には、「良い点(Keep)」「改善すべき点(Problem)」「次回の目標(Try)」の3つの観点で振り返り、フィードバックすることで、新人が具体的な行動に落とし込みやすくなります。(これらの頭文字をとってKPT(ケプト)で振り返るなどと言います。)また、1on1ミーティングを定期的に実施し、新人が困っていることや不安を解消できる場を提供することも効果的です。
4. メンタル面のサポート不足
新人が不安を感じやすい環境では、モチベーションの低下や離職のリスクが高まります。特に、職場の人間関係やコミュニケーションの不足が原因で、新人が孤立してしまうケースもあります。ある会社では、新人が業務をこなすことに必死で、職場の雰囲気に馴染めずにいました。しかし、指導者や同僚は「そのうち慣れるだろう」と考え、特にフォローをすることもありませんでした。すると新人は「自分はここに必要とされていないのでは?」と感じるようになり、結局、数か月で退職してしまい、会社側は新人の定着率向上に向けた改善策を模索することになりました。
改善のポイント: 新人が安心して相談できる環境を作るために、メンター制度や定期的な1on1ミーティングを導入することが有効です。また、新人が職場の雰囲気に馴染めるように、歓迎イベントやチームビルディングの機会を増やすことも重要です。具体的には、OJT期間中に定期的なメンタルケアを実施し、新人が業務以外の悩みも相談できる仕組みを整えると、精神的な負担を軽減できます。さらに、新人同士で情報交換ができる場を設けることで、「自分だけではない」という安心感を持たせることができます。

OJTは、新人を現場で育成するための重要な仕組みですが、適切な計画や指導がなければ十分な効果を発揮することはできません。今回紹介した失敗例からも分かるように、OJTを成功させるためには、計画的な指導、適切なフィードバック、そして新人のメンタル面への配慮が欠かせません。
また、OJTの改善には、職場全体での意識改革が求められます。指導者が単独で努力するのではなく、組織としてOJTを支援する体制を整えることが、新人の成長を加速させ、結果的に職場全体の生産性向上にもつながります。定期的に指導方法を見直し、効果的な教育プログラムを継続的に改善していくことが、長期的な人材育成において不可欠です。
現場のOJTを充実させることは、新人の定着率を高めるだけでなく、組織全体の競争力向上にも寄与します。これからOJTを見直したい企業や現場の担当者は、ぜひ今回のポイントを参考に、自社のOJTをより効果的なものへと進化させていきましょう。
次回は、OJT指導を効果的に機能させるためのポイントについて解説していきます。