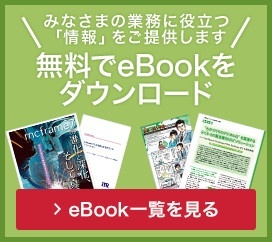技術の暗黙知化

日本の製造業は、高度経済成長期から今日に至るまで、世界に誇る品質と精密さを実現してきました。その根幹には、熟練技能者たちの「技」があります。しかし現在、その技術の多くが次世代へと引き継がれず、いま失われつつあります。
なかでも大きな課題が、「暗黙知」と呼ばれる“言葉にならない技術”の存在です。多くの熟練技術は、マニュアルや手順書には落とし込まれておらず、技能者個人の経験や勘、感覚に基づいています。こうした知識は他者に共有されにくく、技術継承の大きな壁となっているのです。
本コラムでは、全6回にわたり日本の製造業における技術継承をテーマに展開しています。第2回の今回は、「暗黙知とは何か」「なぜ壁になるのか」、そして「どのようにそれを乗り越えるか」という観点から、暗黙知の問題を多面的に整理し、今後の技術継承のあり方を考えます。
暗黙知とは何か?
暗黙知とは、マイケル・ポランニーが最初に提唱したとされる概念で、その著書『暗黙知の次元』(マイケル・ポランニー(著),佐藤敬三(訳),紀伊國屋書店,1980/1/1)において詳しく展開されています。一般的には、目に見えず、言語化されず、文書にも記録されない知識や技能、直感、経験則といったものを指します。
製造現場での暗黙知としては、例えば以下のようなものが挙げられます:
-
熟練工が音や振動から機械の異常を察知する
-
手触りや光沢で加工の精度を見極める
-
わずかな温度や湿度の違いを勘で調整する
これらは一見すると個人の感覚であり再現性がないように思えますが、長年の経験の中で繰り返し実践されることで研ぎ澄まされてきた、高度な判断基準であり、実のところ非常に高い再現性を示します。しかしながら、これらの高度な判断基準や再現性は個人の中に留まっており、それを誰かに伝えるのは非常に困難です。
「見て覚えろ」の限界
ある中堅の金属加工メーカーでは、長年にわたり「見て覚えろ」という文化が根づいていました。現場のリーダー格の熟練者であるAさん(60代後半)は、自身が若い頃にそうして技術を覚えた経験から、後輩にも同じように接していました。新人のBさんはその現場に配属されましたが、作業の意図や細かな注意点が説明されないまま、毎日「やってみろ」「見て覚えろ」「感覚をつかめ」と言われ続け、結局数カ月で現場を去ることになりました。
Aさん自身も悪気があったわけではなく、「実践の中で自分なりのやり方をみつけてほしい」「感覚をつかんでほしい」という善意だったのですが、結果的に技術は継承されず、人材も定着しませんでした。このようなすれ違いは、現場の多くで見られる苦悩の一つです。
かつての日本の製造現場では、「背中を見て学べ」「見て盗め」といったスタイルが主流でした。これは熟練者が細かく教えず、若手が自ら観察し、試行錯誤の中で技術を体得するという、いわゆる「職人」の中では当たり前とされてきた文化です。現在でも製造業のみならず、すし職人や板前、伝統工芸の世界では普通に行われている、職人特有の文化と言えるでしょう。
しかし、このやり方が通用していたのは、すし職人や板前のように、将来自分のお店を構えたいとの高い志がある場合か、長期雇用が前提で時間的余裕があった時代の話です。前回第1回のコラムでも述べたように(第1回コラム参照)、現在の製造現場では以下のような状況が顕在化しています:
-
若手人材の流動性が高く、育成期間が短い
-
少子高齢化により、若手の絶対数が減っている
-
現場の即戦力化が求められるため、経験による学習に頼れない
このような状況では、時間をかけて丁寧に教えたり、何度も繰り返し経験を積み重ねながら、技術を継承していくこと自体が難しくなっています。
また、「見て覚える」やり方は属人性が強く、継承の確実性が低いという構造的な問題も抱えています。
なぜ暗黙知が壁になるのか?
暗黙知の最大の課題は、知識の伝達や共有が難しく、組織全体で知識活用が困難になることです。特に、経験や勘に基づく暗黙知は、言語化や数値化が難しく、属人化しやすい傾向にあります。単なる機械の操作方法のようなものであれば、マニュアル化し、誰もが同じ情報を元に習得できますが、暗黙知はそうはいきません。
例えば皆さんも考えてみてください。「自転車の乗り方」を、全く自転車を乗ったことが無い人に伝えようとした場合、どのように伝えるでしょうか。ハンドルの握り方、ペダルの踏み出し、手足の動かし方、バランス等々、伝えるべきことは多く、また伝え方も人によって様々になるのではないでしょうか。自転車を乗れる人にとってはごくごく当たり前の感覚も、言語にして伝えるのは難しく、指導を受ける側にとっても分かりづらいものになることが想像できます。また、一度伝えたからと言ってすぐに自転車が乗れるようになるわけではありません。何度も練習し、少しずつ感覚をつかむことでようやく乗れるようになるのです。
このように自分の中で当たり前になっている技術や感覚を言語化し、誰かに伝える(継承する)ことは困難であり、特にその人しかできない「職人技」であればあるほど、その難易度は高くなります。結果として、技術継承が個人任せで継続性に欠けたものとなり、技術継承が行われないまま、熟練工が現場を引退すると同時にその技が失われてしまい、組織全体の技能レベルを維持できなくなるのです。
では、技術継承に対して打つ手はないのでしょうか。このような技術継承において一石を投じているのが、野中郁次郎氏らが提唱している「SECIモデル」です。
SECIモデルに学ぶ:知識を共有・転換する方法
「SECIモデル(知識創造理論)」とは、暗黙知を形式知化し、組織の知恵として活用するプロセスを体系化したものです。SECIとは、Socialization(共同化)、Externalization(表出化)、Combination(連結化)、Internalization(内面化)の頭文字を取ったもので、個人が持つ暗黙知を組織全体で共有・活用し、形式知として循環させることによって、価値ある新たな知識を創造する枠組みです。
このモデルは、単に「知識を教える」ことを超えて、知識そのものを“動的に生み出す”ことに重点を置いています。特に製造業の現場のように、言語化しにくい職人的技能が多い環境において、暗黙知の共有と継承のために非常に有効なアプローチと言えます。
SECIモデルの4段階は以下の通りです:
-
共同化(Socialization):熟練者と若手が同じ空間で作業し、体験を通じて暗黙知を共有する
-
表出化(Externalization):暗黙知を言語や図に変換し、形式知として表現する
-
連結化(Combination):表出化された知識を体系化し、マニュアルや教育資料にする
-
内面化(Internalization):形式知を実践によって習得し、自らの暗黙知へと昇華する
この知識変換のプロセスは一度きりではなく、螺旋状に繰り返されることで組織全体の知識レベルが向上していきます。つまり、個人の経験が他者に共有され、それが形式知化された後、再び現場で活用される中で新たな知見が生まれる――この知識のスパイラルこそが継続的な技術革新と技能伝承の鍵となるのです。
SECIモデルは、日本型ものづくりの文化とも親和性が高く、現場における感覚的な技術や、言葉にならない判断基準を、いかに共有し再現性を持たせるかという問いに対する有効な理論的土台となります。

形式知化の工夫と取り組み
ここで一つの形式知化の例を取り上げます。
ある自動車部品メーカーでは、熟練の溶接技術者が定年を迎えるにあたり、ベテランが退職する前に技術を記録しようと、動画とインタビューによる「技術アーカイブプロジェクト」を立上げました。最初は「こんなの撮っても意味ないだろう」と渋っていたベテラン技術者も、自分のこだわりや判断基準を話すうちに、「そういえば、こういう感覚は説明したことがないな」と、自ら技術を言語化し始めました。
その後、若手社員がその動画を見ながら練習し、熟練者によくわからない部分を質問し、フィードバックを受けるスタイルが定着しました。結果として「誰もが最初は下手で当たり前」という空気が生まれたことで、若手も安心して質問できるようになり、離職率の改善にもつながりました。
このように現場でSECIモデルを実現するには、属人的な技能を形式知として可視化・共有するための具体的な実践が不可欠です。例えば、熟練者との対話の場を設けて若手が「なぜこのやり方なのか」と問いかけることで思考の背景を引き出したり、作業の様子を動画や音声で記録し、判断のプロセスを分析・共有したりする取り組みが有効です。また、作業工程をフローチャートとして整理し、重要な判断ポイントやチェック項目を視覚化することや、現場作業を理解・再現・応用できるよう初級から上級まで段階的に整備されたマニュアルを作成することも効果的です。これらの工夫は単なる知識の蓄積にとどまらず、技能伝承を継続的・体系的に行うための組織的な仕組みづくりであり、技術を未来につなぐ基盤となります。
また、技術継承を阻む要因の一つに、「誰が何を知っているか」が把握されていないという問題があります。属人化した技術や経験を可視化するためには、各部署の保有技術や社員ごとのスキル・得意分野を洗い出し、年齢構成や退職予定なども踏まえて、継承が必要なリスク領域を特定することが重要です。こうした情報はスキルマップとして整理し、教育計画や配置転換、人材育成戦略に活用することで、組織的な技術継承の基盤を築くことができます。
おわりに
暗黙知とは、企業にとっての「見えない資産」です。その価値を認識し、形式知へと転換する仕組みを整えなければ、やがて貴重な技術は失われてしまいます。
本稿で述べたように、「見て覚える」だけの文化から、「見せて伝える」文化への変革が必要です。そのためには、SECIモデルに基づいた知識の循環、形式知化の工夫、技術棚卸しによる可視化といった、組織的・戦略的な対応が求められます。
次回は、現場におけるOJTの現状と課題について詳しく掘り下げ、暗黙知の継承を阻む構造的な要因とその打開策を考察していきます。