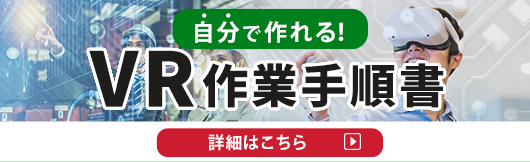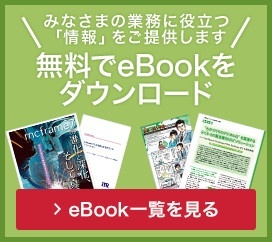OJTの現状と課題

技術が伝わらない時代に、OJTは何を失ったのか
OJT(On-the-Job Training)は、日本の製造業において長年にわたり中核的な人材育成の手法として活用されてきました。実際の業務を通じて知識や技能を習得できるこの手法は、即戦力の育成、現場感覚の獲得、そして暗黙知の継承において非常に有効とされてきました。とりわけ、高度な技能が求められる製造業においては、熟練者の経験を直接学ぶ手段として、OJTは重要な位置づけにあります。
しかしながら、現代の製造現場では、OJTがその本来の目的を果たせなくなっている事例が数多く見られるようになっています。厚生労働省の令和5年度「能力開発基本調査」によれば、OJTを実施していると回答した企業は約95%にのぼる一方で、その内容や成果が「明確ではない」とした企業が46%に達しています。この結果は、OJTが「教えているつもり」「学んでいるつもり」の状態に陥っており、実質的な技術伝承には至っていないことを示唆しています。
第3回の今回は、日本の製造業におけるOJTの実態を紐解き、実例や調査データを交えながら、その課題と打開策について多面的に考察します。また、OJT指導については、「OJTを機能させるポイント」として別途コラムにまとめていますので、ぜひとも参考にしていただければと思います。
「つきっきり型」から「放任型」へと変化したOJT
かつてのOJTは、先輩社員が新人に密着して指導し、手取り足取り教える「つきっきり型」のスタイルが主流でした。ベテランが作業を実演し、その意図やコツをその場で口頭で説明しながら伝えることで、実務に根差した知識と判断力を育てることができていました。
しかし、現代の製造現場では、次のような要因からこのスタイルが成立しなくなっています。
-
現場の人員不足により、育成に割く時間が取れない
-
教える側も自身の業務で手一杯
-
若手への指導が「わからなければ聞いて」と受け身のスタイルに変化
たとえばある金属加工工場では、新入社員に「現場に慣れることが最優先」として、3日程度の導入研修を実施した翌日から生産ラインに立たせ、熟練者による明確な指導がほとんどない中で初歩的な作業に割り当てられていました。その結果、新人の3人中2人が1か月以内に離職。「どんな意図があってやっているのかがよくわからない」「聞きたいけど質問しづらい」「怒られそうで声がかけられない」といった心理的ハードルが、OJTを機能化させる機会を奪っていたのです。
このように、「つきっきり型」から「放任型」への変質は、偶発的な学びに頼る構造となり、技術継承の精度と安定性を低下させる結果となっています。
指導者不足と育成スキルの未整備
OJTを担う側の指導者についても、多くの課題が指摘されています。先般の令和5年度の調査では、人材育成の課題として「育成を担う指導者の不足」が45.6%、「育成にかける時間がない」が45.1%と、上位に並びました。
また、経済産業省の「ものづくり基盤技術の振興施策(令和元年度)」では、中小企業を中心に「教える余裕がない」「教える技術がない」といった育成現場の実態が浮かび上がっています。
実際、OJTを担う多くの先輩社員は、指導法や教育理論を学ぶ機会がほとんどなく、自身の経験則に基づいた「我流」で後輩を指導しています。そのため、教える内容に偏りが生じたり、説明が抽象的で伝わりにくかったりと、指導のばらつきが大きくなりやすいのです。
ある製造現場の班長はこう語ります。
「自分だって、先輩からそんなに具体的に教わったわけじゃない。背中を見て覚えてきた。でも最近はそれで本当にいいのか…と思うようになった。育成したい気持ちはある。でも自分の工程も回さなければいけない。結果的に“見て覚えて”になってしまうんです。」
このように、「教えるスキル」が継承されていないというジレンマは、OJTの弱体化に直結しています。
OJTに依存することの限界とリスク
OJTのメリットは、実務の中で実践的な知識と技能がベテラン社員から学べるほか、教育に係るコストを抑えることができる点にあります。しかしながら、それに過度に依存すると以下のような構造的リスクを招きます。
-
属人化:誰が教えるかによって指導内容や質が大きく変わる
-
バラつき:教える人の得意分野や理解の深さによって指導に偏りが出る
-
継続性の欠如:指導者が異動・退職すればOJTも途切れる
たとえば、ある中堅製造企業では、熟練者の定年退職を機に製品の不良率が一時的に2.5倍に増加しました。ベテランが「背中を見て学べ」としてきた技能が引き継がれておらず、急遽e-ラーニングやチェックリストを導入することで再教育を試みましたが、即効性には乏しく、収束までに半年以上を要したといいます。
このように、OJTだけに依存して技能伝承を行うことは、企業としての技術資産の可視性・再現性を損なうリスクがあり、組織的な継承には不十分であることが明らかです。
仕組みとしてのOJT再設計の必要性
OJTを仕組みとして機能させるには、現場頼みの偶発的な学習から脱却し、計画的・再現的な「企業の育成資産」として再構築する必要があります。以下に、改善のための5つの視点を示します。
1. OJT計画の明文化と個別育成プランの作成
OJTを実施する際には、まず教育対象者ごとにスキルマップを作成し、それぞれの現時点での習熟度に応じた育成目標と達成基準を段階的に設定します。さらに、どの業務のどの場面でどのようなスキルを教えるのかを具体的に言語化することで、「なんとなく教える」「経験で感じ取れ」といった曖昧さを排除し、指導内容のばらつきを抑えることが可能になります。これにより、教える側・学ぶ側双方にとってOJTの目的と手順が明確になり、育成の質と再現性が飛躍的に向上します。
2. OJTリーダーの任命と育成者研修の義務化
OJTを担う指導者の任命にあたっては、従来のように単純な「経験年数の長さ」だけを基準にするのではなく、むしろ「教える力」や「育成への意欲」を重視して選定することが重要です。選ばれたOJTリーダーには、コミュニケーション技法や適切なフィードバックの与え方、指導内容の伝え方を実践的に学ぶための研修を実施します。特に、教え方のロールプレイや模擬指導を取り入れることで、実際の現場でもすぐに活かせる具体的なスキルを身につけられるようにします。このような研修の義務化は、OJTの質の均一化と育成文化の浸透に大きく寄与します。
3. レビューと振り返りの定着
OJTを効果的に機能させるためには、レビューと振り返りを定期的に実施し、それを育成サイクルの中に組み込むことが欠かせません。具体的には、指導者と育成対象者が1対1で行う「1on1の振り返り」を通じて、双方が気づいた点や改善すべき課題を率直に共有する機会を設けます。さらに、こうした進捗状況や課題認識については、教育担当者や人事部門などの第三者も交えて確認を行い、指導が属人化しないように仕組みとしての継続性と透明性を確保していくことが求められます。
4. マニュアル・動画・チェックリストなどの教材整備
OJTを組織的に支えるためには、誰もが一定の品質で学べるような教材の整備が欠かせません。とりわけ、「指導者がその場にいなくても一定レベルの指導が行える」状態を目指し、紙媒体とデジタル両方の形式でマニュアルやチェックリスト、教育用動画といった教材を体系的に用意する必要があります。特に熟練者が持つ感覚的なノウハウやコツなどの暗黙知については、図解や映像といった視覚的な形式で可視化することで、誰もが理解しやすくなり、教える側の負担も大幅に軽減されます。このような教材の整備は、教育の質と効率の両面で大きな効果をもたらします。
5. IT・デジタルツールの活用
OJTの効果を高めるためには、ITやデジタル技術の積極的な活用も重要な要素となります。たとえば、教育履歴の一元管理や習熟度の「見える化」を実現するために、LMS(学習管理システム)を導入する企業が増えており、育成の進捗状況をリアルタイムで把握できるようになります。また、危険を伴う作業や繊細な技術が求められる高精度作業については、AR(拡張現実)やVR(仮想現実)を活用した模擬訓練により、現場さながらの状況下で安全かつ効果的に学習することが可能になります。さらに、作業手順や注意点をモバイル端末で即時に確認できる「作業支援アプリ」の導入も有効であり、現場でのミス防止や即時対応を後押しします。こうしたデジタルツールの導入により、OJTはより柔軟で効率的な育成手法へと進化していきます。

このように、OJTを仕組みとして機能させるには、単なる制度整備だけでなく、指導者・教育者に対する明確な支援とリソース配分が不可欠です。また「技術伝承」を“現場任せ”から“会社の戦略”へと引き上げる経営層の意思も求められます。
OJTを企業の「資産」に変えるために
OJTは、現場の知恵や技術を次世代に受け継ぐ上で、非常に価値ある手法です。しかし現状では、その多くが属人化し、非体系的な状態で運用されており、技術継承の観点では大きな課題を抱えています。
今後求められるのは、OJTを“個々の善意と経験に委ねる文化”から、“企業が設計・運用する育成資産”として再定義し、制度として整備することです。技術継承を支えるには、教える人材の育成・時間の確保・デジタルの活用を含めた、総合的な育成戦略が不可欠です。
次回は、このOJTをより効果的に支援する「デジタル技術・ITツールの活用」について、最新の事例を交えながら考察していきます。