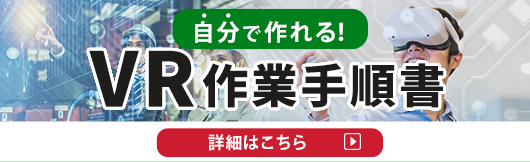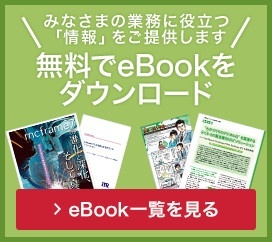デジタル化・IT技術を活用した技術継承の未来

技術継承の課題は「待ったなし」の時代に
製造現場を歩くと、ベテラン作業員の姿が目立つ一方で、まばらな新人の姿。工作機械の音の合間に聞こえてくるのは、「この作業はあと何年続けられるだろうか」というベテランのつぶやき。経営者からは事業の継続について悲鳴にも近い悲観的な声。これは長年にわたり日本の製造業を支えてきた多くの中小製現場において日常的に見られる光景です。
日本の製造業は、長年にわたり世界トップレベルの品質と信頼性を築いてきました。その裏側には、熟練の技能者による精緻な作業と、現場で培われた「暗黙知」の蓄積があります。しかし近年、この強みが揺らぎつつあります。
総務省「労働力調査」(2023年)によれば、製造業従事者の平均年齢は44.8歳と過去最高を記録し、特に技能工では60歳以上の比率が年々上昇しています。経済産業省「ものづくり白書」でも、熟練者の大量退職が迫る一方、新規採用者数は横ばいか減少傾向であることが報告されています。
実際に現場では、ベテランが退職してもその分の人員補充が十分に行われず、一人ひとりの業務負担が増加していると同時に、多品種少量生産が一般化し、一つの製造ラインでも製品仕様が頻繁に切り替わるようになりました。このため、一人の作業者が習得しなければならない技能や作業手順は昔よりも格段に増えています。
ある金属加工工場では、一人の作業者が担当する工程は10年前の倍近くになっていると言います。それぞれの工程で使う機械や工具、品質基準が異なり、切り替えのたびに段取り替えが必要です。熟練者であればスムーズに対応できますが、経験の浅い若手は戸惑い、結果的にミスや手戻りが増えてしまいます。
こうした状況を打破する有効な手段として、デジタル化・IT技術を活用した技術継承が注目を集めています。
第4回の今回は、技術継承におけるITの役割について考察し、実際の導入事例を交えながら今後の技術継承の在り方について考えていきます。
デジタル化が切り開く技術継承の新たな形
製造現場へのIT導入を「DX化」「IT化」等、様々な言葉で表しますが、ここでは「デジタル化」の言葉で統一します。多くの現場で「デジタル化」というと、業務効率化や事務作業の省力化を思い浮かべますが、技術継承におけるデジタル化の役割は、それ以上に大きいものです。ポイントは次の3つ。
-
技能の可視化 ― 暗黙知を見える形にする
-
再現性の確保 ― 誰がやっても同じ品質を実現できる状態を作る
-
学習の個別最適化 ― 習熟度や理解度に応じて学び方を変えられる
これらは従来のOJTでは難しかった領域であり、デジタル化がその壁を突破するカギになります。しかしながら、同時に現場の管理者や監督者からは、「教えたい気持ちはあるが、自分の作業を止められない」「動画で残したいが、撮影や編集のやり方がわからない」「ITを入れると、高額な導入費や現場の負担が増えるのではないかと不安」というような声もよく出てきます。つまり、デジタル技術の現場導入の必要性は理解していても、具体的な進め方や負担感への懸念が足かせになっているのです。こうした状況では、「やらなければ」という危機感はあっても、行動に移す一歩が踏み出せません。
先にも述べたように、現場のデジタル化とは、技能を 「見える化」し、「標準化」し、「共有化」することで、誰でも同じ条件で学べる環境をつくることが目的です。決して高価なツールを導入したり、使いこなすことが目的ではありません。現場の抵抗感を下げつつ導入できる方法も、すでに多くの企業で試されています。いくつか事例を見てみましょう。
①動画で「何度でも見られる指導」を実現
動画は、技能の可視化に最も手軽に取り組める手段です。例えば、旋盤加工の熟練者が部品を削る工程を複数の角度から撮影し、その映像に解説を付ければ、学習者は何度でも同じ場面を繰り返し視聴できます。現場では一度見ただけでは覚えられないことが多く、動画は記憶定着の大きな助けになります。ある金属加工工場では、熟練工の作業をスマートフォンで撮影し、その場で簡単な解説音声をつけるだけの方法を採用しました。専用機材も特別な編集スキルも不要。それでも新人からは「分からなくなったときにすぐ見返せるので安心」という声が上がりました。ポイントは、完璧な映像よりも“すぐ使えること”を優先することでした。
②VR・ARで安全な疑似体験
近年VR(仮想現実)やAR(拡張現実)を導入する現場も増えてきました。VRやARの機材も年々性能がアップしており、価格も安価なものが登場してきています。VRやARは現場の危険作業やミスが許されないような高負荷な工程を安全に再現できるため、現場の安全教育においても非常に有効なツールです。例えば、重量物の組立や高所作業など、失敗すると事故や損害につながる作業は、実機での練習が難しいものです。VRやARであれば、失敗してもリスクはゼロ。繰り返し練習することで、作業者の自信と精度が向上します。
実際にある航空機部品メーカーでは、VRで組立ラインを再現し、新人が仮想空間で部品を組み立てる練習を実施。実際の作業に移行した際、組立ミスが30%以上減少したと言います。担当者も「実機に触る前に一連の流れを体で覚えられるのが大きい」と話していました。
③eラーニングで事前に知識を仕込む
現場の作業は手順だけでなく、その背景にある理論や安全上の理由を理解してこそ応用が利きます。例えば、工程ごとの注意点や基礎知識を短い動画やクイズ形式で事前学習できるeラーニングを導入し事前に学習。技能実習時には「なぜその手順なのか」を理解している状態からスタートできるため、指導時間の短縮にもつながります。
④デジタルマニュアルの導入
前述の通り、製造現場の人員不足と少量多品種対応により、現場の作業員の負荷が高くなっています。その一つに作業マニュアル(作業手順書)の整備があります。膨大な量のマニュアルは覚える側、作成する側、双方にとって相当な労力を要します。結果として更新されないままの古いマニュアルが使われており、作業ミスや効率の低下を招いている例も見受けられます。そこでマニュアルをデジタル化し、タブレットなどの端末に収めることで、作業の動画と組み合わせて現場でマニュアルを確認したり、その場ですぐに修正することが可能となります。ある自動車部品メーカーでは、動画や写真を組み合わせた手順書をタブレットで参照できるようにしたところ、手順ミスが減り、不適合率の低下につながりました。また、手順書の作成においてもAIを活用することで、効率化を図っています。
⑤IoTによる作業データの収集と分析
IoTセンサーを活用し、作業中の温度・振動・速度を記録する事例も増えています。熟練者の「手の感覚」を再現するのは難しいですが、IoTやセンサー技術を使えば数値化できます。例えば、作業中の工具の速度、加える力の強さ、振動のパターンなどを測定すれば、新人と熟練者の差が一目で分かります。金型製造現場では、熟練者と新人の作業データを比較し、数値化された差異をフィードバックしました。新人は自分の作業のどこを修正すればよいか具体的に分かり、習熟期間の短縮につながっています。他にも熟練者の「勘どころ」を再現するために、アイトラッキングやモーションキャプチャを導入する例もあります。
現場とデジタルの融合
これまで述べてきたように、デジタル技術の導入で現場での指導の在り方が変わり、技術継承における様々な問題の解決の糸口になると考えられます。しかしながら、現場のデジタル化は「余計な仕事を増やすのではないか」との警戒感や、逆に「デジタル化さえすればすべてが解決する」との考えがあると導入したとしてもうまくいきません。現場とデジタルの融合を進めるには「何のために導入するのか」「現場のどんな問題を解決したいのか」など、目的を明確化し、以下の3点に示すようなポイントを押さえることで、導入へのハードルを下げ、活用される状態を作ることで促進されます。
-
既存の機材を活用:スマホや既存PCでの撮影・記録から始める
-
現場の声を反映:初期段階で現場の意見を聞き、使いづらい部分は即修正
-
段階的導入:一部工程や1チームから試験的に導入し、慣れたら拡大

技術継承の未来像
近い将来、AIが熟練者の動作や判断の特徴を学習し、それを仮想空間上に再現する「デジタルツイン」技術が、現場教育に組み込まれる可能性があります。新人はAIコーチからリアルタイムの指示や改善点を受け取りながら練習でき、熟練者がそばにいなくても同じレベルの指導を受けられるようになるでしょう。この未来像は、決して遠い話ではありません。今すでに、AIを活用して現場の指導やOJTに活用しようと、動画撮影や簡易センサー計測といった第一歩を踏み出す企業が増えています。デジタル化は、効率化のためだけの施策ではありません。それは、現場の技術を未来に残すための「保険」であり、次世代のための「投資」です。もし今、あなたの現場でベテランの姿が減ってきているのなら、それは変化を始めるサインです。完璧なシステムをいきなり導入する必要はありません。まずはスマホ1台で動画を撮る、その小さな一歩から始めましょう。その映像が、5年後・10年後の現場を支えるかもしれません。
次回は、若手社員の定着とモチベーション向上のための施策について考えたいと思います。