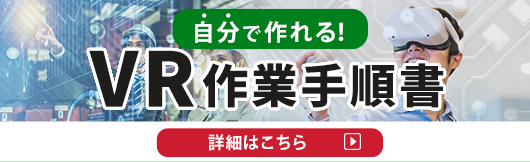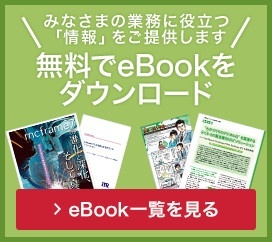技術継承の成功事例と今後の展望

技術継承をめぐる危機と可能性
日本の製造業は、長らく「ものづくり大国」として世界的な評価を受けてきました。その強みの背景には、高度な設備投資や効率的な生産管理だけでなく、現場で磨かれた熟練技能者の経験知がありました。旋盤加工の刃先のわずかな調整、溶接時の音や光から不具合を察知する感覚、あるいは製品検査で目視だけで品質を見極める勘所。こうした「暗黙知」は、数十年にわたる経験を通じて培われ、企業の競争力の根幹を支えてきたのです。
ところが近年、この土台が大きく揺らぎ始めています。総務省「労働力調査」(2023年)によれば、製造業従事者の平均年齢は44.8歳と過去最高を更新し、60歳以上の割合は20%を超えました。大量退職の波が目前に迫る一方で、若手人材の採用・定着は思うように進まず、人材の二極化が深刻化しています。技術継承は「待ったなし」の課題となっているのです。
これまでの連載で整理したように、従来のOJT(On-the-Job Training)だけでは属人化や形骸化が進み、暗黙知を十分に継承することは難しくなってきました。その一方で、動画マニュアルやIoT、VR教材といったデジタル技術が普及し始め、技能の可視化や標準化を可能にしています。すなわち危機の裏側には新しい可能性(=デジタル技術の普及が、技能継承のあり方を根本から変える可能性)も広がっているのです。
最終回の今回はこれまで取り上げてきた技術継承における様々問題を整理し、実際にこうした課題に直面しつつも工夫を凝らし、一定の成果を上げている企業の事例を取り上げます。そして、それらの事例から「成功の共通要因」を抽出し、今後の展望を考察していきます。
製造業における技術継承の課題
これまで本コラムでも多方面から製造業の技術継承における課題を指摘してきましたが、ここで改めて整理してみると、主に以下のような要因があげられます。
-
「若手の定着率低下、指導不足などによる継承の担い手不足」
-
「OJTの形骸化、暗黙知の属人化などによる継承の質の低下」
-
「技術教育の体系化やデジタル活用不足などによる継承の仕組みの不在」
これらの課題をどのようにして克服していったのか、各企業が取り組んだ具体的な事例を見ながらその成功要因を紐解いていきましょう。

事例1:自動車部品メーカー ― 動画とマニュアルで「見える化」を推進
愛知県に本社を置く自動車部品メーカーでは、熟練工の高齢化が進み、定年退職が迫る中で「技能の空洞化」への危機感が高まっていました。特に問題となったのは、長年経験で身につけた仕上げ工程の微妙な感覚を、言葉だけでは若手に伝えられないという点です。
この課題に対して、同社は『動画教材とデジタルマニュアル』を組み合わせた取り組みを導入しました。作業を複数アングルで撮影し、熟練者本人が「この瞬間に力を抜く」「ここで工具の角度を変える」といった解説を加えたのです。さらに、動画と併せてタブレット上で閲覧できるマニュアルを整備し、作業の手順を標準化しました。
若手社員は「動画を何度でも見返せるので、自分の動きと比較できるのが安心」と語っており、また教育担当者も「教える時間が短縮され、指導の質が均一化した」と効果を実感していると言います。
■事例2:精密機械メーカー ― VRで危険作業を仮想体験
長野県の精密機械メーカーでは、危険を伴う現場作業における新人の安全確保が最大の課題でした。従来のOJTでは、熟練工が付き添っていたものの、危険を伴う切削作業や重量部品の組立工程では実際に体験するまでに長い時間が必要でした。
そこで同社は、『VR(仮想現実)技術を活用した訓練プログラム』を導入。実際の工場レイアウトをVR空間に再現し、新人が仮想空間で切削機械を操作することで、危険を伴わずに繰り返し練習できる仕組みを作りました。
導入背景には、「早く現場に慣れてもらいたいが、安全を犠牲にはできない」という現場の切実な声がありました。結果として、新人が現場に出るまでの教育期間は大幅に短縮され、事故発生率もゼロを維持。ある新人は「初めて実機に触れる時も、すでに体が動きを覚えていた」と振り返ります。VRは単なる効率化の手段ではなく、安心して挑戦できる学びの場を提供する役割を果たしました。
事例3:中堅食品加工業 ― アイトラッキングで「勘どころ」を可視化
大阪の食品加工業では、熟練の包丁さばきが品質を左右する重要工程がありました。しかし、その動きは速すぎて言葉では説明が難しく、「見て盗むしかない」とされてきました。
この課題に挑んだのが、『アイトラッキングとモーションキャプチャを組み合わせたプロジェクト』です。熟練者の視線の動きと手の動きを同時に記録し、若手が「どこを見て、どのタイミングで動作しているのか」を再現可能にしたのです。これに基づいて作成された教材は、VRトレーニングと組み合わせて活用されました。
同社には、「若手が自信を持てずに辞めてしまう」という深刻な人材定着の問題を抱えていましたが、実際に教材を使った若手社員は「どこを見ればいいか分かるので、迷いが減った」「簡単に成功体験が積め、自分にもできると思えるようになった」との声が出ています。その結果、離職率は改善され、経営者は「技術だけでなく、若手のやりがいを支えるツールになった」と評価しました。
このように技術継承に対していくつかの事例を取り上げてきましたが、これらの事例には、「暗黙知の見える化」「安全と挑戦の両立」「やりがいを感じさせる」という視点がどうやら共通項となっているようです。単なる効率化やコスト削減ではなく、若手が安心して成長できる環境をつくることが、結果的に技術継承の持続可能性を高めていると考えられます。
技術継承を推し進める成功要因
1. 暗黙知の「見える化」が成否を分ける
3つの事例に共通していたのは、熟練者の持つ「言葉にならない技能」をいかに可視化するかに挑んでいた点です。
自動車部品メーカーでは動画と解説で、食品加工業ではアイトラッキングで、熟練者の「勘どころ」を具体化しました。
ここから導き出せるのは、技術継承において最大のボトルネックである暗黙知を、再現可能な形式に変換する工夫が、成功を左右したということです。
2. 安全と挑戦を両立させる仕組み
精密機械メーカーが導入したVRトレーニングは、新人が「失敗しても安全」な場を確保することで、自信を持って技能習得に臨める環境を作りました。
従来の現場では「失敗は許されない」という緊張感が学びを妨げることも多くあります。これまではある程度許容されていた失敗も、近年では許され難い組織風土もあり、より一層緊張感を高めているように思います。デジタル技術を使えば、危険やコストを気にせずに試行錯誤できるため、若手が安心して挑戦できる環境が整うのです。
これは単なる効率化ではなく、心理的安全性を高める仕掛けとして大きな効果を発揮しています。
3. 若手の「やりがい」を支える仕組み
食品加工業の事例に見られるように、若手社員が「自分にもできる」と感じられる瞬間は、定着と成長の大きな原動力になります。
離職の背景には「学べない」「評価されない」といった失望感が潜んでいることが多々あります。逆に、技術の習得プロセスを分かりやすく示し、小さな成功体験を積み上げられる環境は、若手のやる気を支えることにつながります。
つまり、技術継承の成功要因には、スキルの伝達だけでなくモチベーション設計が含まれることが明らかです。
4. 経営層の関与と現場の納得感
では、上記3つの要素さえ押さえておけば良いかというと、そうではありません。もう一つの重要な要素は、経営層と現場の協力体制です。どの事例でも、現場の「困っている声」を出発点とし、経営層が投資や仕組みづくりを後押ししていました。
トップダウンの押し付けではなく、現場のリアルな課題を丁寧にすくい上げて解決策を設計したからこそ、導入がスムーズに進み、成果が出やすくなったのです。
ここから言えるのは、「経営の意思」と「現場の納得感」の両輪が、技術継承の取り組みを持続的にするということです。
総じて、成功事例に共通していたのは以下の4点です。
-
暗黙知を可視化し、誰もが学べる形にしたこと
-
安全に試行錯誤できる場をつくったこと
-
若手のやりがいを支える仕組みを組み込んだこと
-
経営と現場が一体で取り組んだこと
これらの要因は、今後の製造業における技術継承施策を考える上で、重要な指針となる要素だといえるのではないでしょうか。

■残された課題と展望
これまで見てきたように、多くの企業ではデジタルツールや新しい仕組みの導入自体は比較的スムーズに進むようになってきています。しかし、どの企業でも必ず直面するのが、その後の「定着」という問題です。導入直後は注目を集めても、数か月が経つと利用率が下がり、結局従来のやり方に戻ってしまう現場も少なくありません。その背景には、現場の繁忙さやツールの使い勝手、さらには「なぜこれを使うのか」という目的が十分に共有されていないことがあります。したがって、単にシステムを導入するだけでなく、現場が主体的に使い続けられるように設計する「運用設計」こそが今後の大きな課題となります。
また、デジタル化によって作業記録や習熟度をデータ化する試みが進んでいる一方で、「データと現場感覚がかみ合わない」という指摘も少なくありません。数値上は基準を満たしていても、実際には不安定な動作が残っていたり、熟練者の感覚を完全に数値化できていなかったりするからです。こうした課題を解決するためには、データだけに依存するのではなく、現場の声とデータを突き合わせる「データ+人の目」のハイブリッド型で進める必要があります。
さらに言えば、デジタル技術を活用して技能伝承を進めても、若手が定着しなければ成果は限定的です。若手が「将来どのようなスキルを身につけ、どんなキャリアを築けるのか」のキャリアパスを描けなければ、せっかくの仕組みも持続性を欠いてしまいます。つまり、技術継承と人材育成は切り離せるものではなく、キャリアパス設計の一部として統合的に考えることが不可欠であり、これは今後多くの企業が直面する大きな課題となるでしょう。
加えて、経営層の意識も大きな鍵を握っています。成功事例では、経営層が「技術継承=経営戦略」と位置づけ、投資や支援を積極的に行っていました。しかし多くの企業では依然として「現場任せ」「人材教育はコスト」という認識が根強く残っています。この意識が変わらない限り、取り組みは部分的で短期的なものにとどまり、成果も限定されるでしょう。したがって、今後は経営層が「技術継承を通じて企業価値を守る」という視点を持ち、現場と一体となって推進していく必要があります。
こうした課題を踏まえると、製造業における技術継承は単なる技能の伝達にとどまらず、組織全体が学び続ける仕組みへと進化することが求められます。すなわち、デジタル技術を活用して技能を見える化・標準化し、現場の知見をデータと組み合わせて常に改善を重ね、若手が成長を実感できるキャリアパスを描いて定着につなげる。そして経営層が戦略的に関与し、全社的に学習する文化を醸成していくことが不可欠です。これらの取り組みを積み重ねることで、技術継承は「過去を守る活動」から「未来に進化する活動」へと変わり、企業の競争力を支える強固な柱となっていくでしょう。
技術継承を未来へつなぐために
本コラムの第6回では、技術継承の成功事例と今後の展望について整理してきました。これまで全6回を通じて取り上げてきた課題は、決して一部の企業に限られるものではなく、日本の製造業全体が直面している共通のテーマです。
第1回では、技術継承がなぜ喫緊の課題であるのか、その背景として「技能者の高齢化」と「若手不足」という二重の構造的要因を示しました。第2回では、熟練者の技能が「暗黙知」として属人化している現状を明らかにし、第3回ではOJTの形骸化や属人化の問題を取り上げました。そして第4回では、デジタル技術を活用することで技能の可視化・標準化が進みつつあること、第5回では、その担い手となる若手社員の定着とモチベーション向上が不可欠であることを論じました。(※詳細は各コラム参照のこと)
今回は、これらを踏まえて「実際の成功事例」から学べること、学ぶべきことを紐解いてきました。これまでのコラムの中でも度々紹介してきましたが、デジタルマニュアルと動画教材の導入、OJT再設計とフィードバック文化の定着、ベテランと若手を結ぶ仕組みと心理的安全性の確保等々。いずれも共通しているのは、「技術継承を現場任せにせず、組織の戦略として位置づけた」という点です。
今後、企業が取り組むべき方向性は明らかです。これらの取り組みを一つひとつ積み重ねていくことで、技術継承は単なる「技能の伝達」から「組織の進化」へと変わっていきます。
最後に強調したいのは、技術継承は過去を守るためだけの活動ではないということです。それは未来をつくる力であり、次の世代に新しい価値を生み出すための土台です。製造現場に携わるすべての人がその意義を再認識し、組織的・戦略的に取り組むことで、日本の製造業はこれからも世界で信頼される存在であり続けるでしょう。