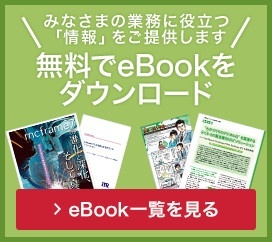安全文化ができるメカニズム

私たちが働く職場には、目に見えないが確かに存在する「文化」があります。それは、日々の業務の中で共有される価値観や行動規範、さらには何気ない会話や態度の中にも表れるものです。その中の一つにあるのが「安全文化」です。安全文化とは、労働者一人ひとりが安全を最優先に考え、行動することを当然のこととして受け入れる職場環境や風土のことを指します。
しかし、この安全文化は一朝一夕にして生まれるものではありません。労働者や管理者の意識、企業の方針、そして組織全体のコミュニケーションが絶えず相互作用しながら、徐々に形成されていくものです。本コラムでは、安全文化がどのようにして構築されるのか、そのメカニズムを探っていきます。企業がどのようにして安全文化を醸成し、労働者全員が「安全第一」を体現する職場を作り上げるのかを考えてみましょう。
安全文化の正体は、その組織に所属する大多数の人に根付いている「当たり前になっている考え方と行動習慣」です。ではその「当たり前」はどのように根付いていくのでしょうか?そのメカニズムがわかれば、安全第一の職場環境や風土を醸成していくことに活用できるはずです。
結論を先に申し上げてしまえば、リーダーが示す言動と上下左右のコミュニケーションの積み重ねで創りあげられるという事になります。さらに言えば、強いリーダーシップによって安全第一のメッセージを打ち出し、それをもとにした個々の自律的な行動によって維持、醸成が図られていきます。

組織にはトップリーダーの「安全と効率がトレードオフになったら安全を優先する判断と行動を取るのが当たり前」というメッセージが、部長・課長・係長・職長・一般社員へとつながるコミュニケーションパイプの中を通っていくことでその「当たり前が根付く」≒「安全文化が醸成される」のです。
そんな当たり前な、と思われるかもしれませんが、ここができていなければそれ以外の打ち手は功を奏しません。例えば、トップの安全メッセージは月次朝礼の時のみ、セクションリーダーの日々の業務における指示が「効率優先」となっているような場合、いくら作業標準指導書を作成し文書管理しようが、残留リスク一覧や残留リスクマップを作成しようが、安全文化醸成の原理原則が崩れていては砂上の楼閣です。社員の中に「安全行動は褒められないが納期遅れは叱られる。効率を優先するのが当然。めったに事故なんで起きないんだし」が当たり前として根付いてしまうことになります。
では、安全文化醸成の原理原則とはどのようなものでしょうか。それは、トップリーダーが「安全第一。何よりも最優先すべきは安全である。」というメッセージをことあるごとに様々な場面で発信する。例えば事業所全体の月次朝礼の冒頭に事業場トップリーダーが「ご安全に」というあいさつの後、安全第一の重要性、効率と安全が対立構造になりどうしても両立が図れない状況になった場合は安全を最優先する判断と行動をするよう具体例を交えて話す。また、自らが頻繁に現場に顔を出し、現場メンバーに「安全と効率がトレードオフになったらまず安全を優先するようにね」と声をかける。脚立を使った高所作業の様子を見て不安全行動と思えるものがあればトップ自らが指摘する・・・等々、「言葉」と「行動」のすべてで安全第一を訴え続ける。その姿勢が、部長、課長、係長、職長へも徹底され、彼らの言動自体もトップリーダーと同じように安全最優先を訴えるものになる。それが継続されることにより組織の隅々まで「安全と効率がトレードオフになったら安全を優先する判断と行動を取るのが当たり前」という認識が根付いていく、これが安全第一の文化が醸成されるメカニズムであり原理原則になります。

また、組織には「権威勾配」が存在します。具体的には、上位者が強い権限を持ち、下位者がその権限に従う傾向が強い状態です。権威勾配が強すぎると、下位者がミスや懸念を報告しにくくなり、事故や問題が発生しやすくなる傾向にあります。この権威勾配を日常からのコミュニケーションで極力なくし、もしミスが起きた際でも、その起こってしまったミスや原因に焦点を当て、個人を責めるのではなく、チームでの学びとして捉えるなど、組織全体として心理的安全性を高め、何でも意見を言い合える状態を作ることも安全文化の醸成には不可欠です。

安全文化の醸成は、単なる取り組みではなく、組織全体が一丸となって進めるべき継続的なプロセスです。この文化が根付くことで、労働者一人ひとりが安心して働ける環境が整い、企業の信頼性や生産性も向上します。安全文化は、トップダウンのリーダーシップだけでなく、現場の声を大切にし、全員が積極的に参加することから生まれます。
今後も、組織全体として安全を最優先に考え、日々の活動の中で安全文化を育む努力を続けることが求められます。こうした取り組みが、結果として組織全体の発展につながり、持続可能な成長の礎となるでしょう。安全文化を築くための一歩一歩が、未来の安心と成功へとつながっていくのです。