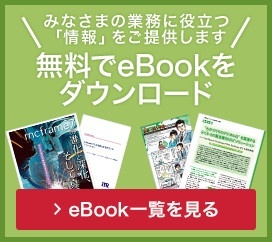人がミス(ヒューマンエラー)をするのはなぜか

職場での人的ミス(ヒューマンエラー)は、私たちが避けて通れない問題の一つです。どれほど経験豊富なプロフェッショナルであっても、時にはミスを犯してしまうことがあります。それは、業務の簡単さや難しさに関わらず、誰にでも起こり得ることです。しかし、このようなヒューマンエラーは、なぜ発生するのでしょうか?その背後には、単なる「不注意」や「うっかり」では説明しきれない複雑な要因が存在します。
本コラムでは、ヒューマンエラーが発生するメカニズムを探り、私たちが日常の業務の中でどのようにしてミスを防ぐことができるのかを考えていきます。エラーの原因を理解することで、より安全で効率的な職場環境を築くためのヒントを見つけていきましょう。
厚労省の分析によると、実際に発生している労働災害の80%に人間の不安全な行動が含まれていると言われています。エラーという結果が生み出される場合、作業環境・施設、設備や機器・教育訓練・企業としての安全への取り組み方針や施策など様々なファクターが絡みあうわけですが、人が直接要因となってエラーを起こすメカニズムについて考えてみます。

ヒューマンエラーというのは「ある状況においてどのように行動すべきか定められている」にも関わらず、「定められていることをしない」または「やってはならないことをする」こと、と言えます。意図的に「やるべきことをやらない」または「やってはならないことをする」のはエラーではなく違反行為ですので、本稿では除外します。
ヒューマンエラーは人が外から与えられた情報を処理する過程で発生しますが、人の脳がどのような過程で情報を処理し行動するのかと言えば、『情報入力(インプット)』→『認知(スループット①)』→『判断(スループット②)』→『行動(アウトプット)』と表現できます。『インプット』と言うのは、外からの情報を見たり聞いたり感じたりという五感で受け取った情報を脳に運ぶことです。『認知』と言うのは「認識する・思考する」などの意味ですがここでは、自分の中にある記憶(学習した内容)と照らし合わせるという意味合いとなります。そしてどうすべきかを『判断』し『行動する』わけです。この情報処理プロセスのそれぞれの段階でエラーが起きる可能性があるわけです。これらのことから、人がミスを起こしてしまうプロセスを4つの段階で整理することができます。
1.インプットエラー
レッドシグナルを見落とす、アラームを聞き逃すなど、情報やデータの入力段階で発生するミスを指します。
2.認知エラー
レッドシグナルは見たが、「これは半年前にも同様のことがあったが大丈夫だったケースだ」と認識してしまう。すなわち、与えられた情報や状況を正しく理解できない、または誤解してしまうことから発生します。
3.判断エラー
「このレッドシグナルは危険な状態」と認知はするものの、本来はまず緊急停止させることが正解であるにもかかわらず、「まず報告し上長の見解を聞くべき」と判断してしまう。すなわち過去の経験や先入観に基づいて誤った判断を下すなど、得られた情報を基に適切な決定や選択ができない場合に発生します。
4.行動エラー
「レッドシグナルを危険な状態と認知し、緊急停止を選択するという判断をしたにもかかわらず、緊急停止ボタンでなく加速ボタンを押してしまう」と言うような、正しい判断をしても、その判断に基づく行動が誤っている場合に発生します。

上記4つのエラーを認識し、例えば行動エラーであれば、ボタン位置を工夫したり、自動停止装置を付けるなど対策を打つことで、ある程度のミスは防ぐことができますが、インプットエラー、認知エラー、判断エラーに対しては、仕組みでの防止は難しいものがあります。
人によりどの段階でのエラーを発生させやすいのかは異なるので、メンバー1人1人の傾向性、つまりどの段階でのエラーが多いのか、どのようなエラーが傾向として多いのかをしっかり把握し、基本トレーニングを土台に、個別の教育訓練や指導・ケアを実施することが大切です。

ヒューマンエラーは、どんなに注意深い人でも避けられないものです。しかし、その原因を理解し、適切な対策を講じることで、エラーを減らすことは可能です。インプットエラーや認知エラー、判断エラー、そして行動エラー、それぞれが発生するメカニズムを知り、組織全体でエラーを防ぐ仕組みを整えることが求められます。
エラーを完全にゼロにすることは難しいかもしれませんが、エラーが発生した際にそれを学びに変える姿勢こそが、長期的に見て安全で効率的な職場を築く鍵となります。ミスが起こる背景を理解し、改善を続けることで、私たちはより良い結果を生み出し、信頼される組織として成長していくことができるのです。