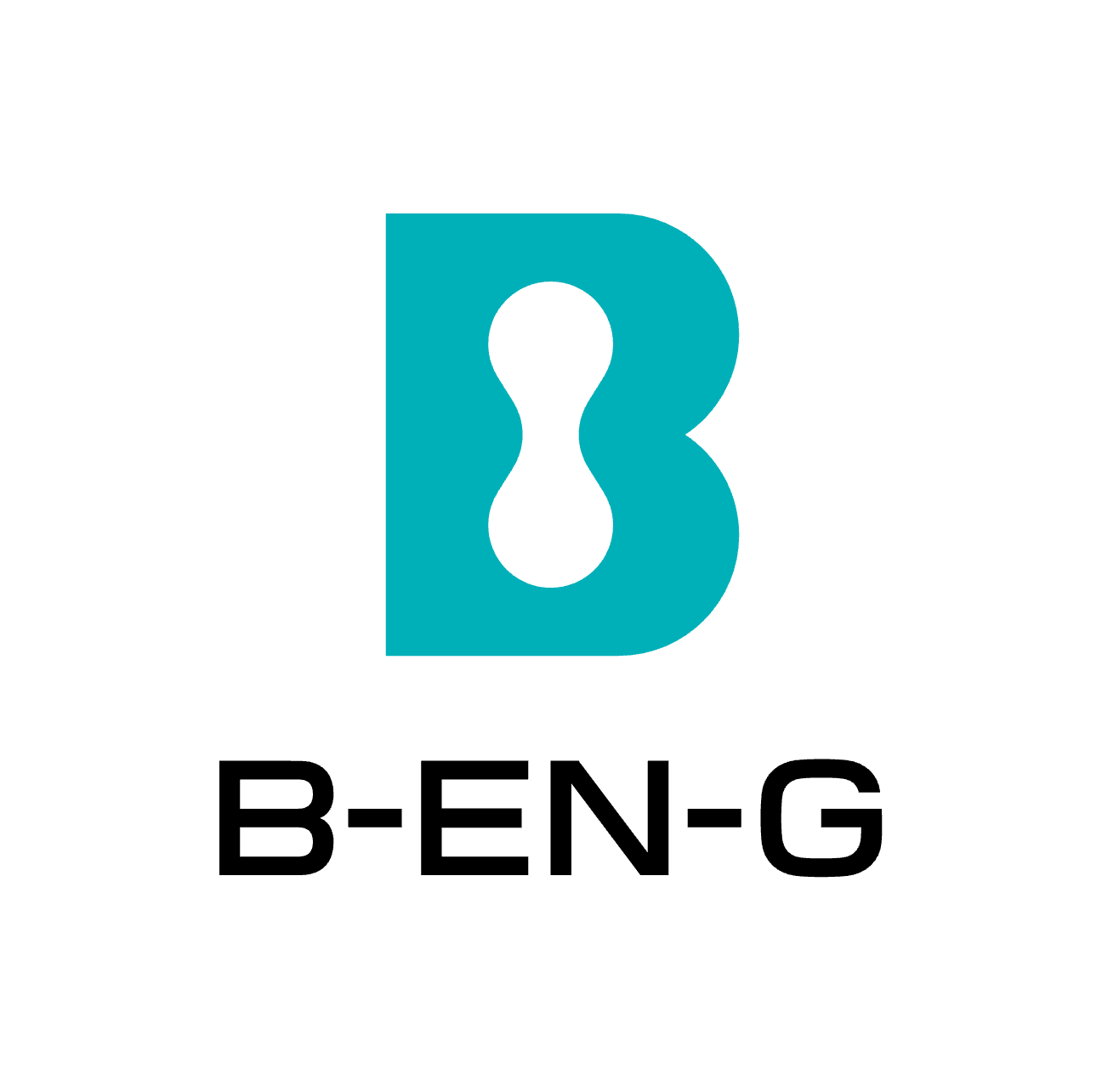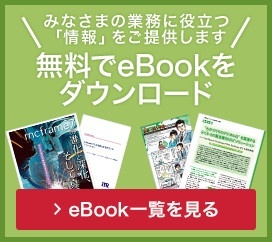【業務のVR活用例】危険疑似体験のVR教材を制作して従業員の危険回避能力を向上

本活用例のポイント
- 普段働く現場の映像を活用することで危険体験のリアリティを強化
- 実際の環境音を組み合わせ、視覚情報と聴覚情報を交えたVRコンテンツを制作
- 映像中にクイズを設け、回答に応じてシーンを出し分けるシナリオも制作
当社のmcframe MOTION VR-learning(以下、VR-learning)でVRコンテンツを内製化し業務課題解決に活かすユースケースを紹介する本コラム。今回は、さまざまなシチュエーションで危険を疑似体験できるVR教材を自社で制作して、従業員への安全教育に役立てるユースケースを見ていきます。
危険疑似体験効果を高めるには、現実感の向上が重要
危険の疑似体験は、安全教育の一環として行われます。安全教育は、本シリーズの「労災事故をリアルに再現して危機意識向上」、「参加者の能動的な体験を促す危険予知訓練(KYT)が可能に」でも扱ったテーマですが、今回はより実践的な内容を深掘りして見ていきましょう。
建築や土木、製造、設備関連などの作業現場には、言うまでもなく転落や衝突、稼働中の機材への巻き込まれ・挟まれ、高温や高電圧の箇所、可燃物や劇物などさまざまな危険が潜んでいます。複数の危険要素が作業者の周囲で同時に存在している場面もありますし、視野の外から突発的に危険が迫ってくることもあり得ます。
しかし人間は、多数の要素を常に意識し続けることが難しいものです。現場で作業する人たちは基本的に各自の仕事に意識を向けているため、差し迫る危険に気付かないこともあります。危険な状況や危険要素への理解不足から、危険要素を適切に認識できないケースも考えられます。さまざまな要因が重なり、危険が迫っていることを認知できないまま事故に遭うケースは少なくありません。
しかし、経験を重ねて学習することで、自身に必要な要素や箇所を即座に認識・確認できるようになり、危険回避や被害軽減につながる可能性が高まります。もちろん、実際に現場で危機に直面する体験を意図的に発生させるわけにはいかないので、教材などを通じて事前に疑似体験しておくことが有効です。
この「危険疑似体験」に用いられる教材は、CGで制作された動画が主流です。多くは抽象化された絵柄を用いているため汎用性が高く、同じ業種や職種の現場に共通して用いることが可能となっています。しかし、その反面として現実感が希薄になりやすく、汎用性の裏返しとして似通った内容に感じられがちです。実感が乏しいと、経験として定着しづらくなる上、経験の長い人にとってはむしろ良くない「慣れ」にもなりかねません。
また、教育効果をより高めるため、次々に新しい教材を用意して受講者に飽きさせない工夫をしたり、自社の現場に即した内容の教材を扱ったりする必要があります。
複数視点で撮影したVR動画に選択肢を設けるなど教材を工夫
この危険疑似体験における課題に対し、既存の教材でなく自社で制作したVRコンテンツを活用することで、教育効果を高めようとする動きもあります。例えば、ある建設・土木系の企業では、工事現場での事故に至るまでの様子を再現したVR映像を撮影し、VR-learningを用いて危険疑似体験教材を制作、安全大会などでVRゴーグルにより社員に視聴させています。
この会社では、それまで使ってきたCG教材に対し、自社の安全教育内容に必ずしも合致しないことや、教材の制作や更新を自社で行えない点などを課題として感じていました。そして、定期的に開催する安全大会では、同じ教材を繰り返し使って教育効果が薄れることを懸念し、CG教材の活用頻度も減っていたそうです。
そこでVR-learningを導入し、VR動画を用いた危険疑似体験教材の制作に乗り出しました。担当するのは安全教育の担当者2名で、事前にシナリオを練り上げてから撮影に臨みます。VRカメラは3台用意し、例えば車両と誘導員といった当事者と、第三者視点とを同時に撮影しており、もちろん周囲の音も同時に収録しています。
さらに、この会社ではVR教材の中に選択肢を設け、安全な結果を選んだ場合には解説シーン、危険な結果に至る選択肢では別途用意した事故映像(市販の映像素材など)へ移るようにしているそうです。
こうして制作した教材の視聴には、VRゴーグルが使われています。目で見る映像と、耳で聞く周囲の音とを総合して、危険に気付いてもらうのが主な狙いです。また、VRゴーグルなら現場事務所に持ち込んで視聴してもらいやすい、という意図もあります。
リアルさとインタラクティブ性が危険疑似体験の効果を高める
この会社では、VR映像を用いたことで、これまでのCG教材より格段にリアルな危険疑似体験を実現しました。視聴した人は、実際に自分自身にも起こりうることのイメージをより実感できたでしょう。
また、シナリオを工夫して選択肢を盛り込んだことにより、実際の現場での事故に至る経緯や危険に気付いて回避するためのポイントが、より的確に伝わるようになりました。繰り返し視聴する場合でも、別の選択肢を選ぶことで結末が変わるため、マンネリ化しづらくなると期待されます。
VR-learningでは、選択肢を表示するだけでなく、画面内の特定箇所をクリックすると別コンテンツがポップアップ表示されるなど、インタラクティブ性を高める機能が備わっています。これらの機能を上手に生かすことで、危険疑似体験教材の幅も広がるはずです。
なお、VR-learningで制作したコンテンツはPCなどでも視聴できる上に、ストリーミング版ライセンスを購入することで配信も可能になります。遠隔地の現場にいる社員が空き時間に視聴するなどの使い方もできるため、危険疑似体験の機会を増やすこともできるでしょう。
また、集合教育として、PCから大画面ディスプレイに出力した教材を1人が操作しつつ、多人数で視聴するといった形態も可能です。自社の体制、教育指導方針などに合わせ、柔軟な使い方を選ぶことができます。
業務のVR活用例 記事一覧
- 労災事故をリアルに再現して危機意識向上
- 参加者の能動的な体験を促す危険予知訓練(KYT)が可能に
- 作業標準書への活用で、標準作業の習得、非定常作業にも対応できる人材を育成
- 新人教育や安全教育に活用し、手順書より優れた効果を発揮
- 熟練作業者の手順と視線を可視化。技能伝承にも活用
- 危険疑似体験のVR教材を制作して従業員の危険回避能力を向上
- 安全を担保する作業マニュアルをVRで自社制作して効率的な安全教育を実現
- 教育機関での現場実習の補助教材をVRで作成 現場の雰囲気や留意事項を先取り
- 職場見学へのVR活用で労働力確保と求職者とのミスマッチ防止に貢献
- 業務にまつわる技能資格などのVR教材を内製化 学習効率を高めて合格率アップ
- 実務に直結する技能講習や資格試験の内容をVR教材で予習 効率的な学習が可能に