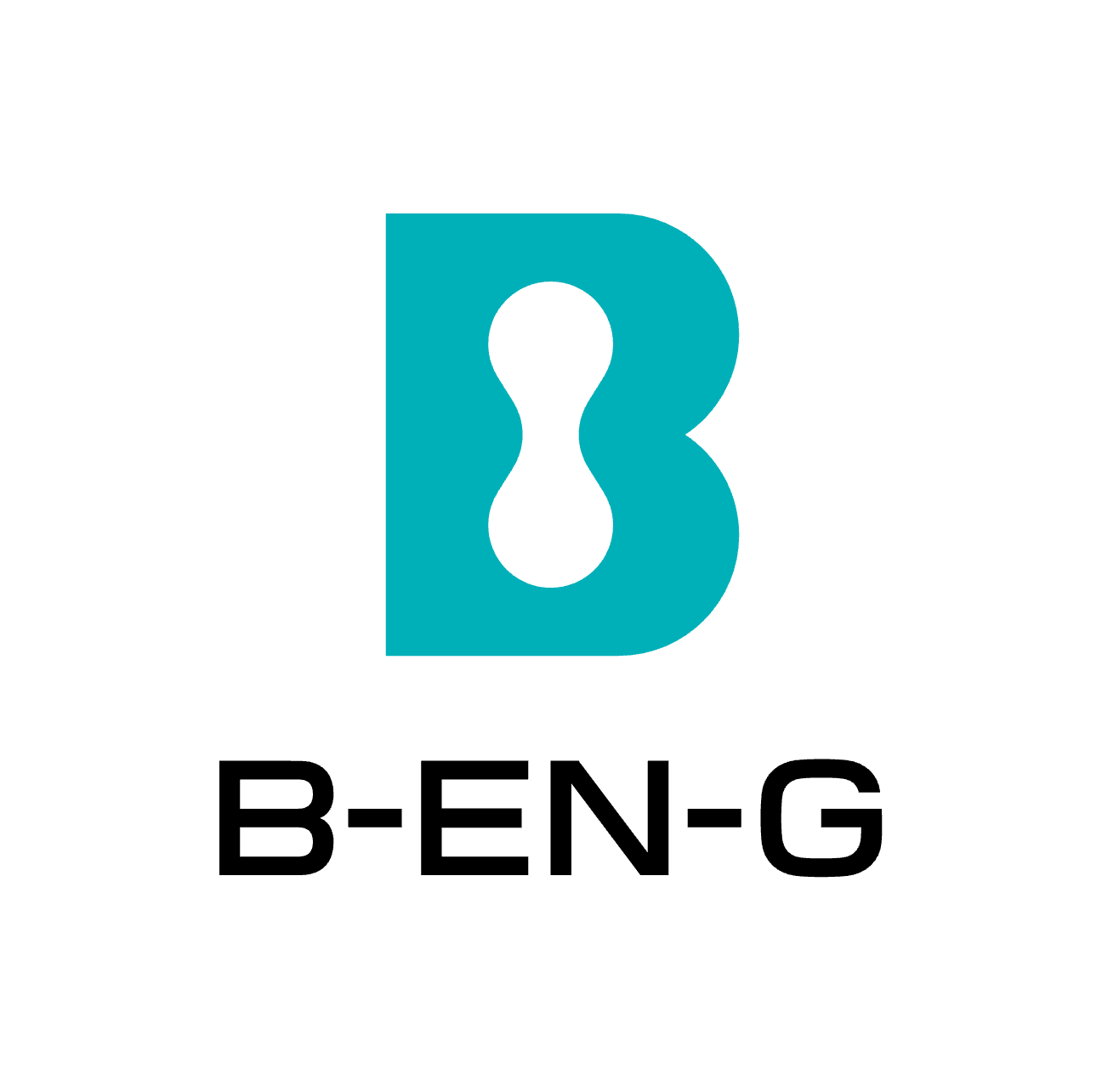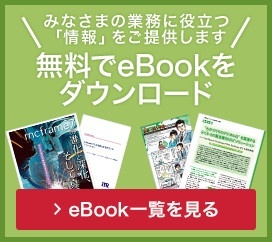【業務のVR活用例】職場見学へのVR活用で労働力確保と求職者とのミスマッチ防止に貢献

本活用例のポイント
- バーチャル職場体験で求職者とのミスマッチを防止
- 機密情報を管理しながら職場体験を実施可能
- 遠方の求職者にも情報を提供でき、新たな労働力確保に貢献
当社mcframe MOTION VR-learning(以下、VR-learning)のユースケースを紹介する本コラム。今回はこれまでのように従業員を対象とした内部向けではなく外部向け、特に求職者への情報提供にVRを役立てるというものです。VRコンテンツで社外へ情報提供する活用例およびそのメリットを紹介します。
人材獲得や定着促進に重要な現場見学を実施できないことも
労働人口の減少が続く日本では、今後より多くの企業で人材不足が慢性化すると懸念されます。これまで働いていた人たちが高齢化して次第に現場を離れていく中で、企業は新たな人材を獲得して労働力を確保し続けなければなりません。
ところが、いくら募集をかけても人がなかなか集まらない、せっかく獲得した人材が定着せず短期間で退職してしまう、といったケースも依然として多く見られます。企業間における人材獲得競争は激しさを増し、人材の獲得や定着という課題が、より企業の人事担当者の頭を悩ませる時代に突入しているのです。
人材の売り手市場と言われている現在、企業は求職者からみた自社の魅力を高めるため給与や福利厚生などの待遇をできるだけ改善したり、新たに入社した人たちが長く働き続けてくれるような労働環境に変革していくなど、さまざまな対策を講じる必要があります。
また、求職者が事前に具体的な業務内容や職場の様子を把握できるよう、情報提供をすることも企業が担う重要な役割です。人材と職場とのミスマッチが入社後に顕在化し、新入社員が早期退職することになればお互いに損をするばかりです。このような残念な結末を少しでも減らすためには、求職者に仕事の様子をあらかじめ具体的に理解してもらうことが望ましいと言えます。
その方法としては職場見学やインターンシップなどが定番ですが、職場によっては実施が困難な場合もあります。例えば、現場に危険要素があって関係者に高度な研修を行わなければ立ち入りを認められない場合や、業務上の機密情報が数多くあって情報漏えい対策のため見学者の受け入れが困難な場合、また求職者が遠方在住で気軽に現場を訪れることが難しいなど、さまざまな理由があるでしょう。そもそも、未経験者である求職者の見学を受け入れる時、企業は現場にも負担を強いることになってしまいます。
VRコンテンツでリアルな職場見学の機会の提供が可能に
求職者の見学受け入れが容易でない現場においては、こうした課題を解決するために、VRコンテンツを使って職場見学を実施する動きがあります。例えば、ある自動車関連メーカーでは、作業手順や安全教育の教材としてVR-learningを活用しており、これを求職者向けのバーチャル見学にも応用しようと検討をしているそうです。
VR-learningなら、撮影を業務時間外に行い、業務上の機密情報などが動画内に写り込まないよう工夫したり、ぼかし処理などを行ったりすることで、現場への負担を最小限にしつつリアルなバーチャル見学コンテンツを制作することができます。工場内のさまざまな場所で撮影を行った上で、VR-learningで多彩な選択肢や説明、ポップアップ映像などを盛り込めば、求職者に豊富な情報を伝えることが可能です。
企業説明会などの場にVRゴーグルを持ち込んで、自社で制作したコンテンツを求職者に視聴してもらえば、求職者が実際に足を運ぶことなく職場の雰囲気や業務内容を知ることができるというわけです。視聴者の数が多い場合であっても、映像をプロジェクターや大画面ディスプレイに映すことで、多人数で同時に視聴することもできます。この使い方ならVRコンテンツをローカルで管理できるため、機密情報の管理という観点からも有効です。
そのほか、VR-learningのストリーミング版ライセンスを購入することで、遠方の求職者にもリモートで動画を視聴させることもできます。VR-learningの使い方次第では、求職者との接点を格段に広げることができ、より多くの人材の獲得に貢献できることでしょう。
会社紹介動画ではバーチャル職場体験の代用が難しい
このようなVRを使った職場見学を、自社の紹介として一般的に用いられるような会社紹介動画などで代用できないかと考える企業もあるかもしれません。しかし、VR動画による職場見学と会社紹介動画は性質や制作目的が異なります。
具体的には、会社紹介動画は主に求職者が就職先選びの段階で参考にするものですが、VR動画による職場見学は、実際に応募を検討する段階に入った求職者が参考とするものです。そのためVR動画の制作に当たっては、入社後の業務内容をより具体的にイメージできる内容を心掛けることが望ましいでしょう。
また、VR-learningの活用には、社内の人員だけでVRコンテンツを制作できるという大きなメリットがあります。社外に制作を委託するよりコストを抑えられる上に、機密情報の漏えいといった懸念も軽減されるでしょう。VRコンテンツの内容の修正も随時行うことができるため、自社内の最新の業務環境を反映させ続けることが可能です。
VRコンテンツを用いたバーチャル職場見学は、製造現場のみならず、人の立入が容易でない僻地や危険を伴う環境での業務など、さまざまな職場の体験に役立つでしょう。求職者とのミスマッチを防ぐためにも、VR-learningの導入を検討してはいかがでしょうか。
業務のVR活用例 記事一覧
- 労災事故をリアルに再現して危機意識向上
- 参加者の能動的な体験を促す危険予知訓練(KYT)が可能に
- 作業標準書への活用で、標準作業の習得、非定常作業にも対応できる人材を育成
- 新人教育や安全教育に活用し、手順書より優れた効果を発揮
- 熟練作業者の手順と視線を可視化。技能伝承にも活用
- 危険疑似体験のVR教材を制作して従業員の危険回避能力を向上
- 安全を担保する作業マニュアルをVRで自社制作して効率的な安全教育を実現
- 教育機関での現場実習の補助教材をVRで作成 現場の雰囲気や留意事項を先取り
- 職場見学へのVR活用で労働力確保と求職者とのミスマッチ防止に貢献
- 業務にまつわる技能資格などのVR教材を内製化 学習効率を高めて合格率アップ
- 実務に直結する技能講習や資格試験の内容をVR教材で予習 効率的な学習が可能に