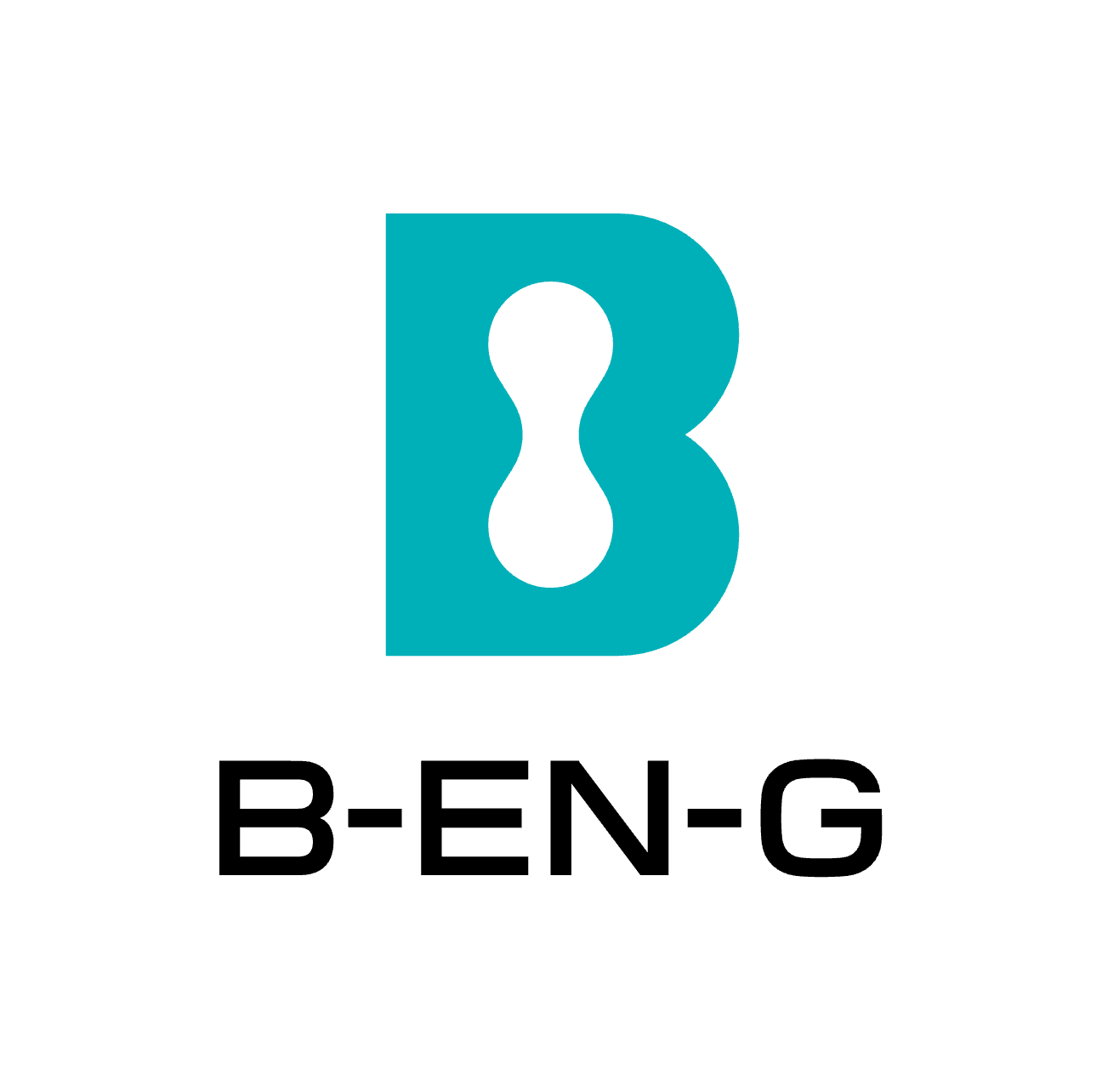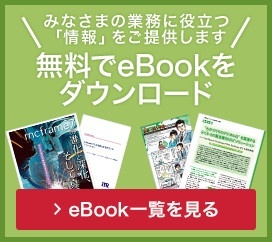【業務のVR活用例】身近な場所で撮影された実写VR映像の防災教材が受講者に気付きを与える

本活用例のポイント
- 受講対象者に合わせて教育コンテンツの作り分けが可能
- 地域ごとの特性を踏まえた防災教育を実施
- クイズゲームのように楽しみながら防災活動に参加
当社のmcframe MOTION VR-learning(以下、VR-learning)による業務課題解決のユースケースをご紹介する本コラム。今回は、避難行動に重点を置いた防災コンテンツでの活用例をご紹介します。VR-learningの特徴を生かして、災害の仮想体験・避難訓練を高度化するためのポイントをお伝えします。
多種多様な自然災害が起こる日本では防災教育は一筋縄ではいかない
日本は、多種多様な自然災害に見舞われることが多い、世界でも有数の自然災害多発地域です。地震や台風、豪雨、豪雪といったさまざまな自然災害は、日本のどこであろうと生じる可能性がありますが、その土地ごとの地形や地質、地下構造などといった条件に応じて、発生しやすさが変わります。災害によって求められる対策は異なるため、それぞれにあった防災活動のあり方を考える必要もあります。
防災活動の一例が避難行動です。河川氾濫や津波に対しては、高台への避難が原則となります。土石流など土砂災害の危険が高まっている場所では、沢沿いや傾斜地など危険が予想される範囲からできるだけ遠ざかる必要がありますが、その際には土砂の流れていく方向を意識しつつ移動することが重要です。ただし、夜間や土砂降りなど視界が悪い状態で屋外へ避難することは新たなリスクをもたらすため、屋内で少しでも安全な場所へ移動するなどの対応が望ましいとされています。
また、どの時点で避難行動を開始する判断を下すかも難しい問題です。河川氾濫や土砂災害の場合は降水量が大きな要因となり、ときには気象庁や自治体などによる避難勧告や避難指示が間に合わなかったり、届かなかったり、想定外の箇所で堤防や斜面が崩れるといった例もあります。より多くの命を守るためには、最適な行動を見極め、適切なタイミングで適切な行動を取ることが重要です。
しかし、避難行動1つとっても、周辺環境や時間帯などの状況に応じてさまざまな選択肢が考えられ、その中で迅速かつ適切な判断・行動が求められることから、防災教育は一筋縄ではいかないものです。さらに、受講者に対して同じような内容を繰り返し教えても、マンネリ化してしまい教育効果が高まらないといった点も、防災教育における大きな課題です。
受講対象に合わせた教育コンテンツの作り分けも可能
こうした課題に対し、受講者一人ひとりが災害を体感することを重視した防災教育を行っている研究者たちもいます。VRをはじめとするXR技術も、防災教育への応用が検討されています。受講者たちが災害時の状況を臨場感ある映像で体験でき、一人ひとりが防災活動を「自分ごと」として意識しやすい、といった効果を期待してのものです。
実際に、VR-learningも、防災教育研究の中で用いられています。福井大学の取り組みでは、暴れ川で有名な九頭竜川流域に住む小学生などを対象として、水害からの避難をテーマとしたVR教材の開発、実証に乗り出しています。
VR-learningは、360度映像を撮影できる360度カメラを用いた映像を使って、受講者がよく知る場所をテーマにしたVRによる防災教育コンテンツを容易に制作できます。例えば、小学生への防災教育に自分たちが通う小学校で撮影した映像を使うといったことが可能です。また、制作した教材の編集も素早く容易に行えるため、受講者たちの反応を見て、より良い教材へと改善していくことができます。
なお、この福井大学の事例ではVRゴーグルの対象年齢以下である小学生を防災教育の受講対象として想定しているため、VRゴーグルは使わず、コンテンツを大画面ディスプレイなどに映し出して視聴させているそうです。また、小学生に過剰な恐怖心を与えてしまわぬよう、災害のリアリティは低めに表現し、むしろゲーム感覚で楽しめるよう工夫しているといいます。
VR-learningは、コンテンツ内に選択式の設問を設けることができるため、クイズゲームのように楽しみながら防災活動に参加してもらうことができます。学習した内容の習熟度など、防災教育への効果が期待できます。
もちろん、大人を受講対象にする場合は、災害時の状況をよりリアルに表現したり、シビアな設問を設けるなどの工夫を施したりすることも考えられるでしょう。そういった、受講対象ごとに最適なコンテンツを作り分けることも、VR-learningは難しくありません。
企業・自治体の防災活動にも役立つ
福井大学の事例記事で紹介した使い方は、教育機関におけるものですが、もちろん他の場合であっても応用できます。例えば自治体が、地域ごとの特性に合わせた防災訓練用VRコンテンツを作ることも可能でしょう。
企業でも、防災訓練の一環として、VR教材を使った事故対応訓練を行うなどの使い方が考えられます。工場や倉庫などの事業所の多くは事業所内の消防組織を設け、定期的に訓練を行うなどしていますが、VR教材があれば従業員が個別に、空き時間などにコンテンツを視聴して防災意識を高めることができるはずです。
事業所内のさまざまな場所で、多様な災害状況を再現すれば、従業員がそれらを学習して状況に応じた判断を下せるようになるのではないでしょうか。
業務のVR活用例 記事一覧
- 労災事故をリアルに再現して危機意識向上
- 参加者の能動的な体験を促す危険予知訓練(KYT)が可能に
- 作業標準書への活用で、標準作業の習得、非定常作業にも対応できる人材を育成
- 新人教育や安全教育に活用し、手順書より優れた効果を発揮
- 熟練作業者の手順と視線を可視化。技能伝承にも活用
- 危険疑似体験のVR教材を制作して従業員の危険回避能力を向上
- 安全を担保する作業マニュアルをVRで自社制作して効率的な安全教育を実現
- 教育機関での現場実習の補助教材をVRで作成 現場の雰囲気や留意事項を先取り
- 職場見学へのVR活用で労働力確保と求職者とのミスマッチ防止に貢献
- 業務にまつわる技能資格などのVR教材を内製化 学習効率を高めて合格率アップ
- 実務に直結する技能講習や資格試験の内容をVR教材で予習 効率的な学習が可能に